
【後編】谷川 嘉浩
夢中になれない訓練をされてきた私たちが「没頭」を手にいれるには
常時接続の世界で哲学者の言葉が持つ意味
2023.07.27
常時接続の世界で、私たちは一生懸命、自らを忙しくしています。「時間がない」となげくものの、すごい早さで出回る情報から遅れたくないし、話題に乗り遅れたら一人ぼっちになってしまうかもしれない……。
人がたくさん集まっているからこそ寂しい。そんなしんどさから逃れようとSNS断食をしても、不便さもあって続かない現代人。孤独な時間を取り戻し、自分と対話するにはどうしたらいいのでしょうか。
前編では、哲学者の谷川 嘉浩さんに「趣味を持つ」お話を聞きました。でも、趣味を持つことでますます忙しくなったり、他人が気になってしまったりすることもありますよね。趣味を持つことにどんな意味があるのでしょう。谷川さん、教えてください。
( POINT! )
- 趣味で没頭する時間が大事
- 没頭することで新しい思考に気づける
- 現代人は夢中になれないよう訓練されている
- コミュニケーションがあっても、没頭するときは一人
- 利益がなくても、夢中になってしまう時間は無駄じゃない
- 誰が言う・いつ言うかも大事なこと
- ちょっと遠いところで考えられるのは哲学の強み
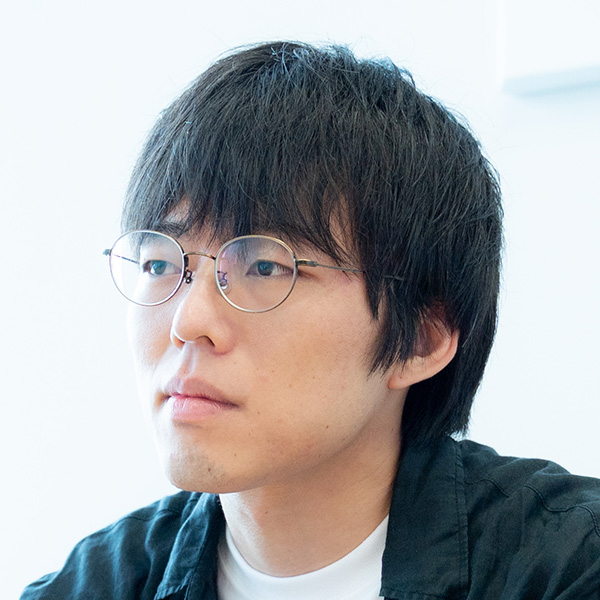
谷川 嘉浩
1990年生まれ。京都市在住の哲学者。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師。専門は哲学など。メディア論や観光学、社会学といった他分野の研究や、デザインの実技教育に携わるだけでなく、企業との協働も多数。著書に『信仰と想像力の哲学:ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)、『スマホ時代の哲学:失われた孤独をめぐる冒険』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、共著に『〈京大発〉専門分野の越え方:対話から生まれる学際の探求』(ナカニシヤ出版)など。
楽しくて、思わず没頭してしまう「趣味」
より軽快に「孤独」と付き合う手がかりは「趣味」にあると前編でお聞きしました。『スマホ時代の哲学』でも紹介されていましたが「新世紀エヴァンゲリオン」の加持リョウジがスイカを育てるみたいなことですよね。
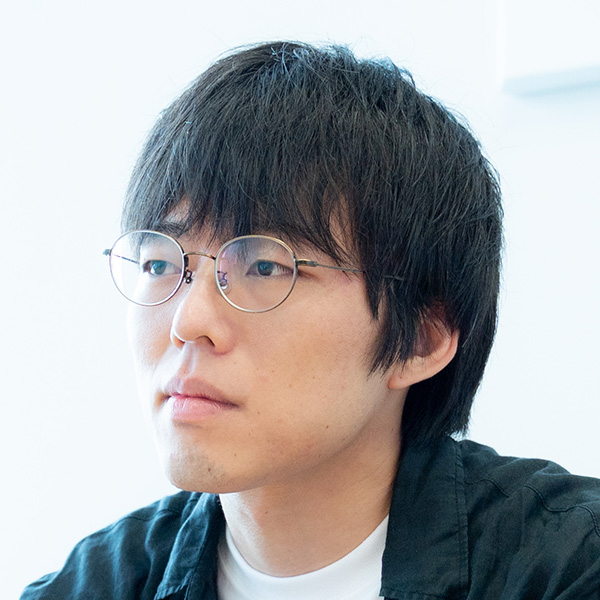
谷川
世界の危機や自分の命の危険が目前にあるにもかかわらず、加持はのんきにスイカを育てていましたね。何かの役に立つことが目的とは思えないし、誰かを依存的に求めているわけでもない。
本業の役に立つとか、副業として利益を得るといった実利はなさそうです。楽しそうですが。
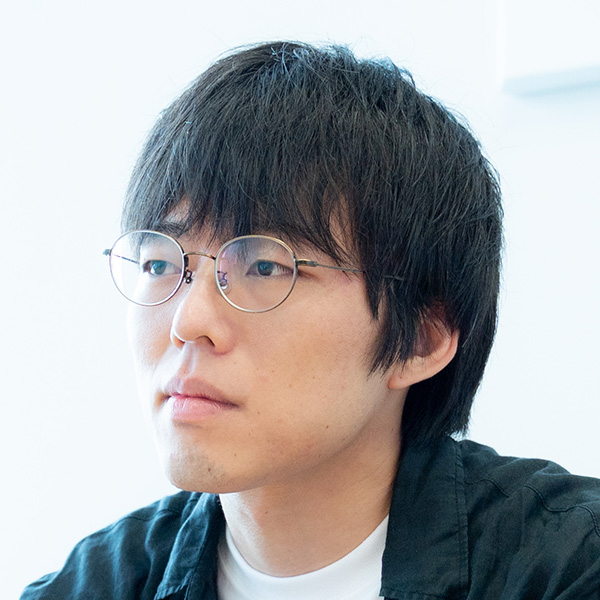
谷川
楽しくて、思わず没頭してしまうことが大事なんじゃないですか。畑を作ることでも、料理を作ることでもいい。大事なのは、そういう趣味を楽しむプロセスで、いろいろなことを考えるってことだと思います。
走ることを例にするとわかりやすいかもしれません。走っているときに、誰かと喋り続けることは物理的にできませんよね。アイコンタクト的にコミュニケーションをとることがあっても、走ってるときは「一人だ」と感じるはずです。結果的に、そこには孤立や孤独があるわけです。
走っているときって、なにかについて悶々と考えてるわけではないんだけど、これまで考えたことや、それに対してこれまで思ったことがないような感情、新しい視点とか、いろいろなものが湧き起こってくる。そういうものが、自己対話の芽になるんですよ。
でも、趣味を見つけられない人もいますよね。趣味仲間と楽しそうに過ごしている人がうらやましいとか。
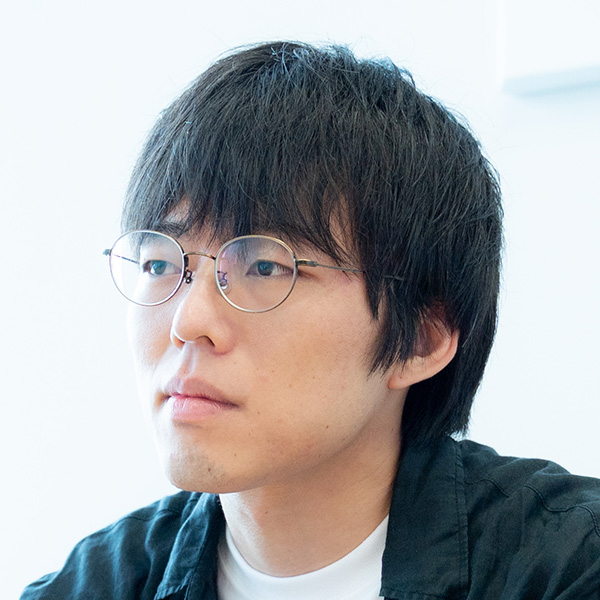
谷川
それは、自分の関心を見失いやすい生き方を選ばされてきたからだと思います。子どもは「将来やりたいことは?」と聞かれることが多いですよね。それにもかかわらず、勉強や習い事では、関心を無視してベルトコンベヤーみたいに課題が目の前に運ばれてくる。何か他に没頭していることがあっても、大人は子どもの文脈をぶった切って、とにかく勉強させてしまう。
子どもを例に挙げましたが、もちろん働いている大人でも事情は同じです。個人の関心の流れを無視して、ぶつ切りのタスクを与えられるなんて、仕事じゃ日常茶飯事ですよね。そんな扱いに慣れてしまっているわけだから、とにかく夢中になれるものなんて、なかなか見つかりづらいですよ。

夢中になることを規制されてきた現代人
夢が野球選手だったとして、それとこれとは別なのでとりあえず勉強しましょうとか?
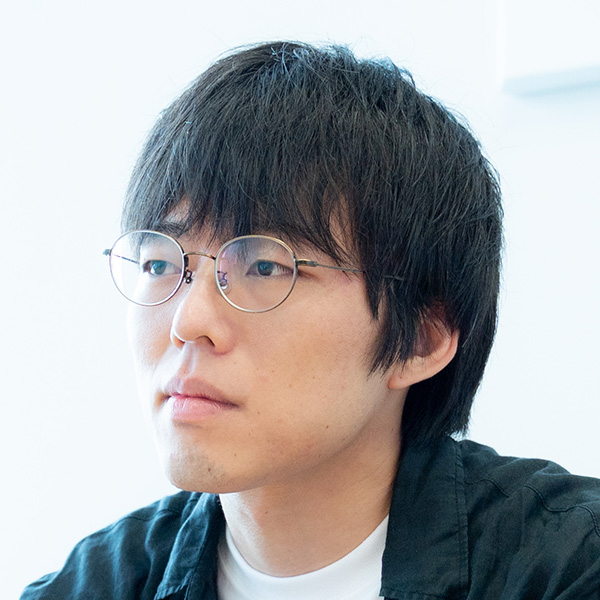
谷川
そうですね。ただ、自己啓発本みたいに「夢を追い求めましょう」「情熱に従いましょう」という話がしたいわけではなくて、自分の関心を探索したり、気になることを調べたりすることに夢中になることが、子どもにとってもむずかしいことだと確認したかったんです。
たとえば、数学に夢中になる人ってしばしばいますが、そのまま数学をやり続けたくても、「数学の時間はここまでで、次は国語」となる。その切り替えに付いてこられない子どもは、夢中になるものを持っている子どもではなく、融通がきかないし言うことを聞かない「厄介な子ども」として扱われてしまう。私も大学で教員をやっているから、教員一人ひとりに合わせて授業を組むことの難しさは体感としてわかるんですけど。
それでも強調しておきたいのは、子どもをこんなふうに扱うことは、自分の関心を抑圧して、目の前のことをやるノウハウを教える連続講座を履修させているようなものです。一生かけてそんなものを教え込んでいるかもしれないわけです。そう考えると、「大人が子どもに手渡す教育がこれでいいのか?」と疑いも生まれてきますよね。
自分の関心を探したり育てたりする時間を手放してきたんだから、大人になったときに、それ自体を目的にして夢中になれるような活動がない、つまり「趣味」がないというのも、そりゃそうだろうな……という気持ちです。
しかも、そういう状態で、無理に「やりたいこと」を探すと、いかにもやりたいことっぽいこと、いかにも趣味っぽいことを探してしまうでしょうね。
趣味っぽいものというと、やっている人が多くて講座が用意されているような。
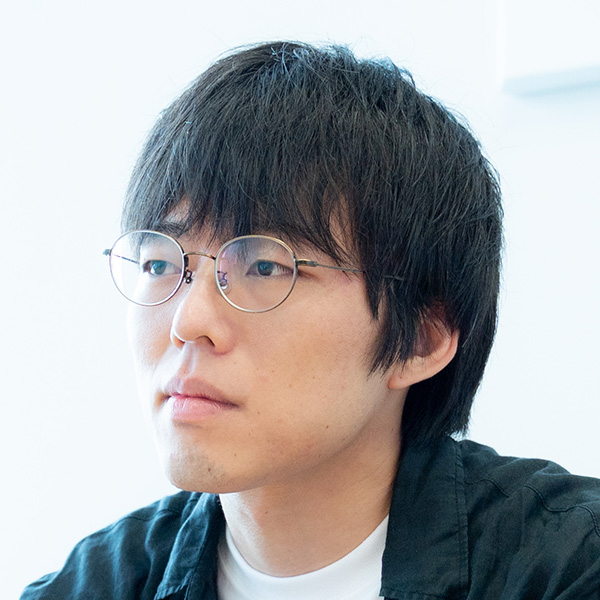
谷川
退職後に男性がそば打ちを習い始めるとか、そういうやつですね。老年期の活動として、盆栽やゲートボールが「いかにも」になっているのもそうです。
ただ、自分の子ども時代を思い返せば、同級生の中には、周囲に制止されてもずっと自由帳に絵を描いていた人や、別の科目の間もずっと数学の問題を解き続けていたような人もいましたよね。私が言っている「趣味」は、そんなふうに遊びみたいに突き詰める活動のことなんですよ。周りの都合とか、周囲の人の好みとかは関係がない。
逆に、自覚せずに趣味を持っている場合もありますよね。仕事なんだけど面白くて夢中になってやってしまうとか。
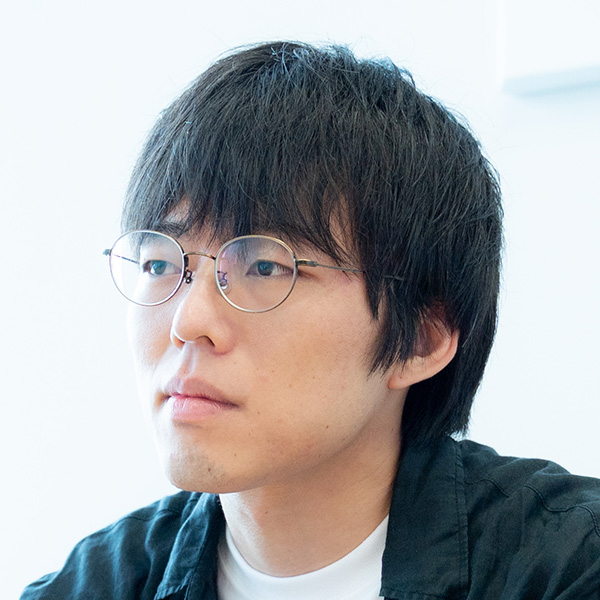
谷川
ね。仕事なのにお金や評価を忘れて、突き詰めても仕方がないと頭でわかってるのに力を注いでしまうことってありますよね。そのときには、仕事であっても一種の趣味なんですよ。世間を離れて仕事に没頭しているときって、湧き上がってくるいろいろな考えや思いに向き合うことができますよね。

評価やコミュニケーションがあっても、没頭するときは一人
夢中になれる力は、どうしたら持てるでしょう。
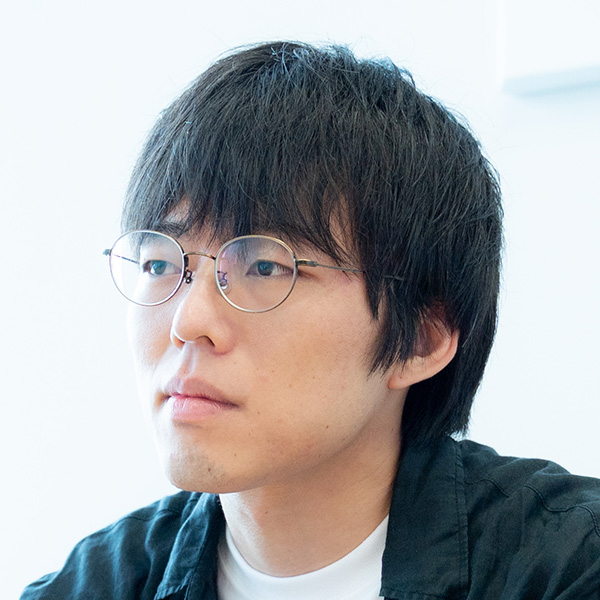
谷川
以前、学生から公園で見かけた親子の話を聞いたことがあります。女の子が転んで地面に手をついてしまい、お父さんが「大丈夫?」と聞いたら、女の子は「あつい」と答えたんです。それを聞いたお父さんは女の子の隣に行って地面を触って「あついね」と言った後、木陰に行って「こっちは?」と言ったんだそうです。
そしたらその女の子はそこに行って「あつくない!」と言い、もはや転んだことは忘れていろんな場所を触って「あつい」「あつくない」と楽しみだしたんです。こうやって関心は育っていくんだと思います。
たまたま生まれた関心を、大事にしてくれたんですね。
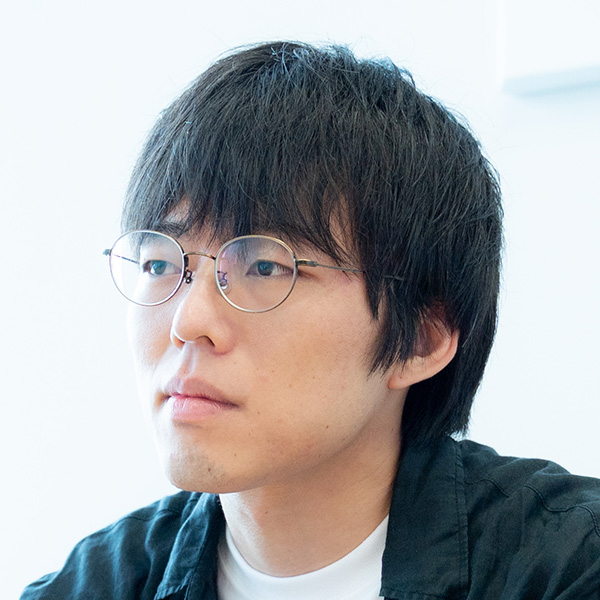
谷川
そのお父さんみたいな声かけが日常的に続いていたら、その女の子はきっと自分の関心に向き合って生きていけますよね。親子関係だけでなく、友人同士や社内でも同じです。誰かが誰かの関心に配慮しないと、趣味の芽は生まれないと思います。
社会全体としては、子ども時代から働き始めた時期まで、ずっと自分の関心を育てないようにと方向づけているわけです。だからこそ、お互いに関心を育て合う、他者が関心を育てるために気遣いをする、そういう親切さが必要なんだと思います。そういうコミュニケーションにコストをさけない共同体は脆弱ですよ、やっぱり。
配慮し合うのではなく、自分の評価だけを気にしてしまうことがあります。作品を発表すると制作のモチベーションにつながるけれど、評価が目的になってしまうかもしれません。
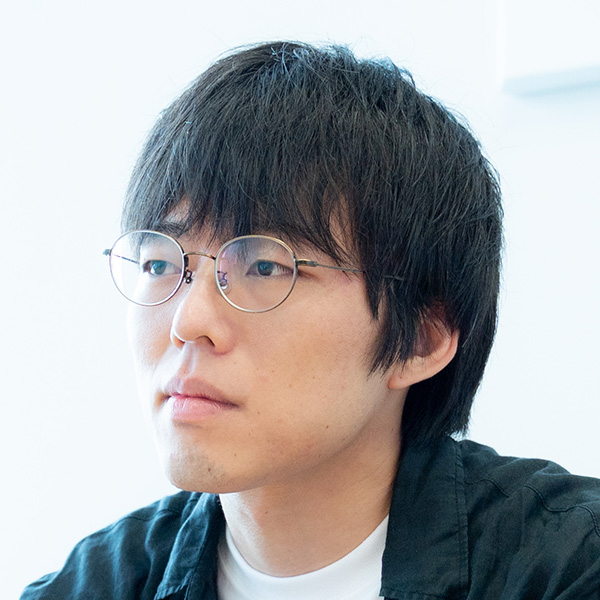
谷川
作品制作をするタイプの趣味なら、不特定多数の人のいるSNSや創作プラットフォームだけでなく、特定の人たちがいるコミュニティに参加するのがいいと思います。そうすると、SNSよりは評価が前景化しにくいはずです。
大学時代に短歌をやっていたのですが、自分一人だけでやっているとうまくならないし、つくるきっかけが続きにくい。でも、歌会という制作発表の機会を定例開催しているコミュニティがあって、それが助けになるんですね。創作の選択肢も増えるし、意外な言葉に出会えることもある。
それに、共同体に入ったとしても、短歌を作っている瞬間は結局孤独なんですよね。だから、創作のハイライトはコミュニケーションになりえない。不特定多数のいるインターネットではなく、特定の人たちがいるコミュニティに参加すると、そのことが見えてくると思います。

誰が言う・いつ言うかも大事。哲学者の言葉が響くわけ
趣味の活動でもSNSで他人と比べて落ち込んだり、YouTuberとして動画を配信したりと、つい忙しくしてしまいがちです。そんな現代人が哲学を学ぶには、どんな方法がありますか?
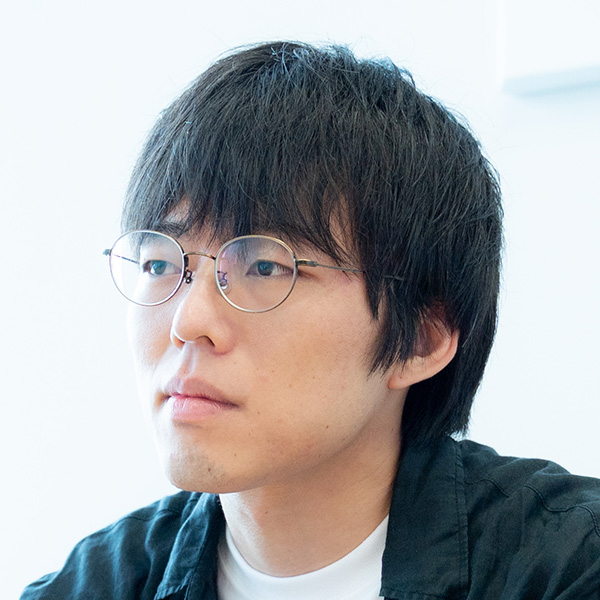
谷川
本を読んだり読書会を開いたりしてもいいし、誰かのファンになってもいいですね。
たとえば、ニーチェファンになるとか?
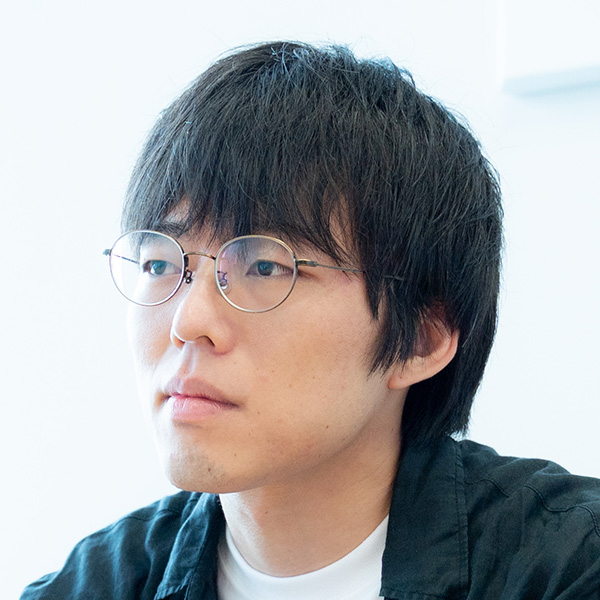
谷川
そういうことです。亡くなっている哲学者でもいいから、一旦「この人ピンとくるかも」という人のファンになってみる。すると、その人のいろんな文章を読んだり、その人を扱った文章を集めたりと、収集が始まりますよね。そういう仕方で、哲学に参加していくことができます。
哲学者の言葉は、かっこいいですよね。でも、同じ言葉を親から聞いたら腹が立つと思うんです。それは理解していないからですか?
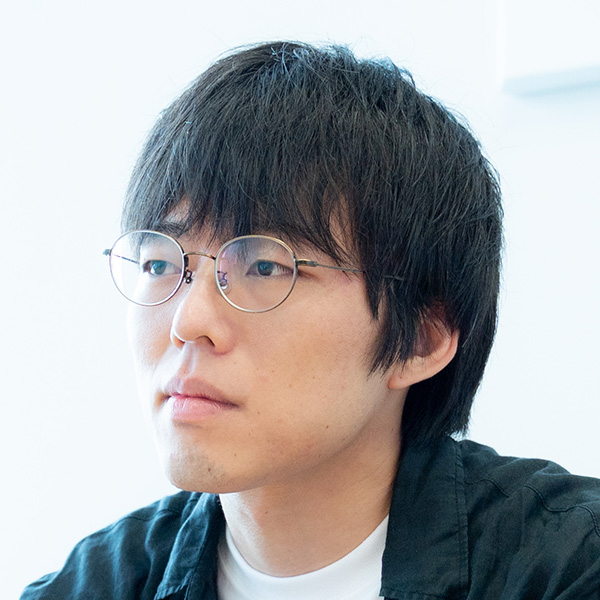
谷川
実はそれが哲学のよさでもあるんですよね。私たちと哲学者とのあいだに、距離があることが大事なんです。親や上司だと近いから、耳に痛いことを言われると反発するということがありますけど。
世の人は「何が語られているか」という内容が大事だと思っているかもしれないですけど、実は、「誰が言うか」も大事なことなんですよ。言葉は文脈によって受け取られ方が変わるものです。話を戻すと、哲学者って、私たちの人間関係から遠いので、あまり余計なことを考えずに受け取りやすいところがあるんですね。
距離があるという点では、哲学とフィクション作品は似ています。自分の家族関係について直接悩むと心は波立つけど、是枝裕和監督の映画みたいに、家族を主題にした作品を観て感想を作り上げていくと、距離をとって「家族」という主題について考えられますよね。
距離をとってワンクッション置いたとしても、そこで考えたことは、だんだん自分にフィードバックされてきます。孤独を通じて、趣味を通じて自分と向き合うといっても、直接心のやわらかいところを触る必要はないんですね。何か別のものを介して、思考を進めていくこともできるわけです。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]工藤 真衣子






