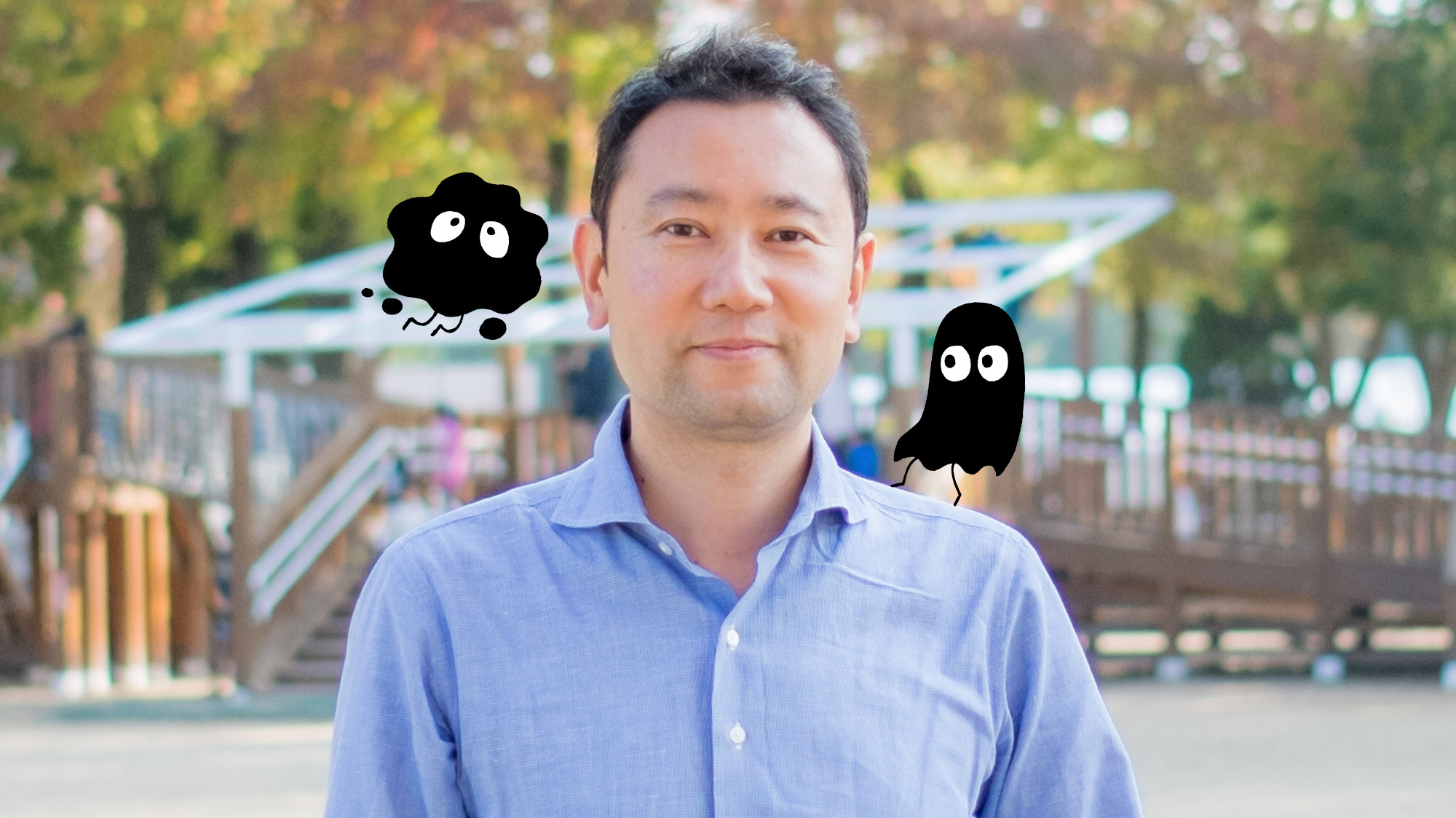
【前編】松村 圭一郎
「私の名前はずっと同じ」は、当たり前じゃない?
文化人類学の見地から考える、「私」の曖昧さ
2021.09.22
「生まれた瞬間から私は私であり、これからも私であり続ける」。当然のことのように聞こえますよね? でも、この記事を読んだあと、その考えは変わる……かもしれません。本記事でお届けするのは「アイデンティティの一貫性」にまつわるお話です。
インタビューにこたえていだたいたのは、岡山大学の准教授であり、文化人類学者である松村 圭一郎さんです。「個性について語るなら、『すべての人は一貫したアイデンティティを持っている』という考えから見直さなければならない」。豊富なフィールドワークの経験に基づいた松村さんの「個性論」に耳を傾けてみましょう。
( POINT! )
- 「名前はずっと変わらない」は当たり前ではない
- 日本人の名前が「変わらなくなった」のは、明治時代に入ってから
- 国民国家が個人のアイデンティティを固定化した
- エチオピアでは、名前も宗教も自由にコントロールできる?
- 個性は「見つけるもの」ではなく、「つくられていくもの」

松村 圭一郎
1975年、熊本生まれ。京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有と分配、貧困や開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社)、『基本の30冊 文化人類学』(人文書院)、『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、『はみだしの人類学』(NHK出版)、共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)がある。
エチオピア人の名前は、ころころ変わる
松村さんはこれまでエチオピアを中心に、さまざまな国でフィールドワークを重ねてきたと思います。そんな松村さんに「個性」についてうかがってみたいと思いまして。

松村
ちょっと遠回りをして、アイデンティティの一貫性に関するお話から始めましょうか。いきなりですが、エチオピアの人の名前ってころころ変わるんですよ。
どういう意味ですか?

松村
日本では子どもが生まれたらまず名前をつけて、基本的には一生その名前で生きていきますよね?でも、エチオピアではそうじゃない。名前が変わっていくこともそうなのですが、同時に複数の名前を持っている人も大勢いる。たとえば、ある家族に子どもが生まれたとして、おじいちゃんが「この子の名前はこうだ」と言うけど、お母さんが「それは嫌だ。私はこう呼ぶ」みたいな。
人によって、違う名前でその子を認識している?


松村
そうです。なぜそんなことになるのかというと、いわゆる戸籍や出生届がないからなんですね。その子が大人になると成人名がつけられて、パブリックな場ではその名前で呼ばれるけれど、たとえば幼馴染は小さいころの名前で呼び続けているということもあって。つまり、関係性によって名前が変わるんです。そんな話を学生たちにすると「名前が変わったり、複数あったりするなんて理解できない」と。
私も教え子のみなさんと同じ気持ちです(笑)。

松村
でも、日本も明治時代になるまでは同じ状態だったんですよ。たとえば明治時代以前、武家に子どもが生まれるとまず幼名が付けられます。その後、元服(現在でいう成人)を期に「諱(いみな)」と呼ばれる正式な名前を与えられるのですが、諱が使われることはほとんどなく、普段は通称で呼ばれる。そして、この通称は生涯を通じてころころ変わるんですよね。
では、明治時代になってから、日本人の名前はころころ変わらないようになったということですか?

松村
はい。政府が諱と通称の併用を廃止するなど、姓名に関する法律を整えたわけです。簡単に言ってしまえば「名前は一人一つ。ころころ変えるのも禁止」とし、現在の戸籍の基盤となる全国的な戸籍制度をつくりあげました。
ではなぜ、明治政府がそのようなことをしたのかというと、近代的な国民国家、つまり国民全員を把握して中央集権型の国家をつくり上げるためですね。
戸籍に登録してある名前をころころ変えられてしまうと、国家は国民を管理できなくなりますもんね。

松村
そう。国民国家の成立によって、アイデンティティが固定化され、国民一人ひとりが自己の一貫性を獲得することになった。国家が「あなたはずっと、あなたのままでいなさい」ということを規定したわけですね。
名前も、年齢もコントロールできる?

松村
もう少し説明を加えます。アフリカにルワンダという国があります。これはルワンダに限らないことですが、民族ってかなり線引きが曖昧で、柔軟なものなんです。しかし、先ほど言ったように、個人のアイデンティティが定まらないと管理するのに不都合が生じます。
だから、ベルギーがルワンダを植民地として支配する際、身分証明書を発行して「この人は何族である」ということを明記したんですよね。そうして、ルワンダの人びとの民族意識は固定化した。
国民を管理しようとする主体が国民個人の一貫性を求めた結果、「私は◯◯族である」あるいは「私は◯◯という名前の個人である」という意識が人びとの中で固定的なものに変わった。

松村
私たちは名前が変化しない、言い換えればアイデンティティが固定化されていることが当たり前になった社会の中に生まれ育ったので、その状態に違和感を覚えませんよね。でも、「自分という存在には一貫性がある」という考え方自体、国民国家が生み出した神話のようなものなんです。
元々、「私」は絶えず変化し続けるものだったのですね。

松村
現在でも自らのアイデンティティは自由にコントロールできるものだと考えている人びともいます。先ほど、エチオピアの人びとは複数の名前を同時に持っているという話をしましたが、それは自分の意志や状況に応じて、どんな名前を使いたいか、どの名前で呼ばれたいかを選べる、ということなんです。
それに、最近ではエチオピアの女性たちが中東の湾岸諸国に出稼ぎに行くようになったのですが、そうするとパスポートが必要ですよね。パスポートを取得するためには、身分証明書が必要なわけですが、先ほど言ったように出生届がないので、村の役所に言って、好きな名前と年齢を言ったら身分証明書がもらえるんですよ。
確認のしようがないですもんね。

松村
つまり、名前も年齢も、自分の都合がいいように変えられてしまうんです。名前によってキリスト教徒なのかイスラム教徒なのかは明確に分かってしまうのですが、出稼ぎに行く時、たとえばイスラム教徒の方が都合が良さそうであれば、それまでキリスト教徒の名前を使っていた人が、イスラム教徒名に変えてしまうとか。
もちろん、信仰は簡単に変わらないと思いますよ。でも、名前などで示される表向きのアイデンティティは自由にコントロールできるものだと考えられているわけです。
そうすると、日本のような社会に生きている私たちと、エチオピアのような社会に生きている人びとでは「個性」の捉え方も大きく違いそうですね。


松村
そうですね。個性の問題を考えるとき、前提になるのは「すべての個人は一貫したアイデンティティを持つ存在である」という考え方や「他者とは異なる存在として『自分』がいる」という感覚だと思うのですが、そういった前提から考え直さなければならないと思うんです。個性の土台となる「個人」とは何なのかといったところから、議論をはじめる必要があると思いますね。
個性は環境や周囲との関係性が決める
とはいえ、現実的な問題として、この国には個性について悩んでいる人がたくさんいると思っています。「個性を発揮しろ」と言われる一方、「周囲と合わせることを覚えなさい」と言われたりするなかで、「どうすればいいんだよ……」と。

松村
大学の学生と接するなかでも、そういった悩みを抱えている人は少なくないと感じています。「個性的であれ」「個性的になりすぎるな」。そんな2つの相反する圧力を受けているような状態ですよね。
学校の中に限っていえば、「個性的であることはいいけど、教員が手を焼くほど個性的にはならないでね」ということ。社会全体に目を向けても、「多様性が大事」と言いながら、個性と認められるのは個人が属している共同体にとって不都合ではない個性のみ。その枠をこえてしまうものは、排除しようとする力が働いているように思います。
個人が所属する組織や社会の側が、自らに都合の良いように「個性」の定義を決めてしまっているわけですね。

松村
そもそも、個性って相対的なものなんですよ。たとえば、日本において「電車の中で楽器を弾きながら歌うこと」は個性として認められますかね?
うーん……「他の乗客の迷惑になるから」と止められそうな気がしますね。

松村
でも、それがたとえばイタリアの電車の中の話であればどうでしょう。実際にローマなどでは、そんな場面をよく目にしますし、誰もそれを変だとは思っていない。何が言いたいのかというと、「日本は不自由で、イタリアは自由だ」ということではなく「何が個性なのかは、環境や周囲との関係性が決める」ということで。
つまり、個人の中にある特性が「個性として発揮される」のではなく、周りとの関係性の中で「個性として可視化される」んですよ。「大学デビュー」という言葉がありますよね。これは、大学に入学した途端、キャラクターや服装が変化することを揶揄する言葉ですが、大学デビューするのはある意味では当然だと思うんです。なぜなら、環境や付き合う人が変化しているわけですから。
では、社会や組織が個性を規定するのは、ある意味当たり前なのでは……?

松村
おっしゃるとおりです。そして、それは言い換えれば「個人の特性を活かすも殺すも環境次第」ということでもある。だから、学生たちには就職活動の面接で「あなたはどんなことができますか?」と聞かれたら、「こんなことやあんなことができます」と言うのではなく、「御社の環境は私の能力を活かせますか?」と聞き返した方がいいと言っています。そんなこと言ったら落とされるのかもしれませんけど(笑)。
企業が学生に強みを聞いたり、何ができるのか知ろうとするのは、個性を固定的なものだと捉えているからだと思うんですよね。でも、その人が持つ特性が個性として活かされるかどうかは、周囲との関係性や環境によって決まる。つまり、個性を発揮させられるかどうかを問われるのは、その個人ではなく、企業の側なんです。
個性は「見つける」ものではなく、「つくられる」もの
環境にかかわらず「この人はこういうことができる人だ」と決めつけてしまうような見方をしている。

松村
学生側も、常に自分の個性が分かっていないと不安なんだと思うんです。「すべての人はその人固有の個性を持っている」という考えを前提とすると、個性が分からないということは、自分という存在の価値が否定されることになってしまいますから。
自分が「何者であるか」が分からない不安というか。


松村
でも、先ほどのエチオピアの人びとの話をしましたが、そもそも「すべての人が一貫したアイデンティティを持っている」という考え方自体が、国家が生み出した幻想のようなものなわけですよ。アイデンティティを固定的なものだと考えてしまうから、"自分に固有の個性”が分からないと「自分は一体何者なんだろう……」と悩むことになる。
仮にすべての人がその人のアイデンティティとなるような絶対的な個性を持っていたとしても、20年そこそこ生きただけでそれが一つに定まっているわけがないと思いますし、何者かである必要もないと思いますけどね。
なるほど。

松村
採用する側の大人たちも、経験的には分かっているはずなんです。自分が大学生のとき、はっきりと「自分が何をできるのか」「何が自分の個性なのか」分かっていた人なんて、ほとんどいないはずで。でも、なぜか人を見て評価する側に回ると、多くの人が「すべての人には固有の個性があるはずだ」と思い込んでしまうんですよね。
もちろん、企業側も決められた採用数の中で最適な人材を確保するために最大限の努力はしていると思いますし、学生たちが個性に悩むすべての原因を国家や企業に求めるつもりはありません。でも、就職活動の中でさまざまな情報に振り回されて、自らを取り繕うとしている学生たちの姿を見ていると、「個人の特性を活かす側」の考え方を変えなければならないと感じるんですよね。
就職活動の時点で「何者かであること」を求めるような姿勢というか。

松村
個性って、自分の歩みを振り返ってはじめて分かるものだと思うんです。自分の中にあった個性が徐々に「見えてくる」のではなく、さまざまな環境で、さまざまな人と関係する中で徐々に「つくられていく」。だんだん年を取ると「これが自分の個性だ」と言えるようになるかもしれませんが、それははじめからあったものが見えるようになったわけではないんですよ。
問題は、多くの大人たちが「はじめからあった個性が見えるようになったわけではなく、徐々につくり上げられた」ことを経験しているにもかかわらず、そのことを言語化し、理解できていないことだと思うんです。だから、特に若い世代が個性や「自分らしさ」が"見えないこと"に悩み、苦しんでいるのだと思います。
[取材・文]鷲尾 諒太郎 [編集]小池 真幸
前編では、松村さんがフィールドワークを通して実際に出会ったエチオピアの人びとのアイデンティティの捉え方や学生たちが抱える悩みを通して、個性を巡る問題とその原因を紐解きました。後編では、そんな思い込みを越え、「自分らしく」生きていくための方法をうかがいます。重要なことは「身体をもって、世界と交わりつづけること」。そして、それは「多様な他者とともに生きるためのキーにもなる」と松村さんは言います。





