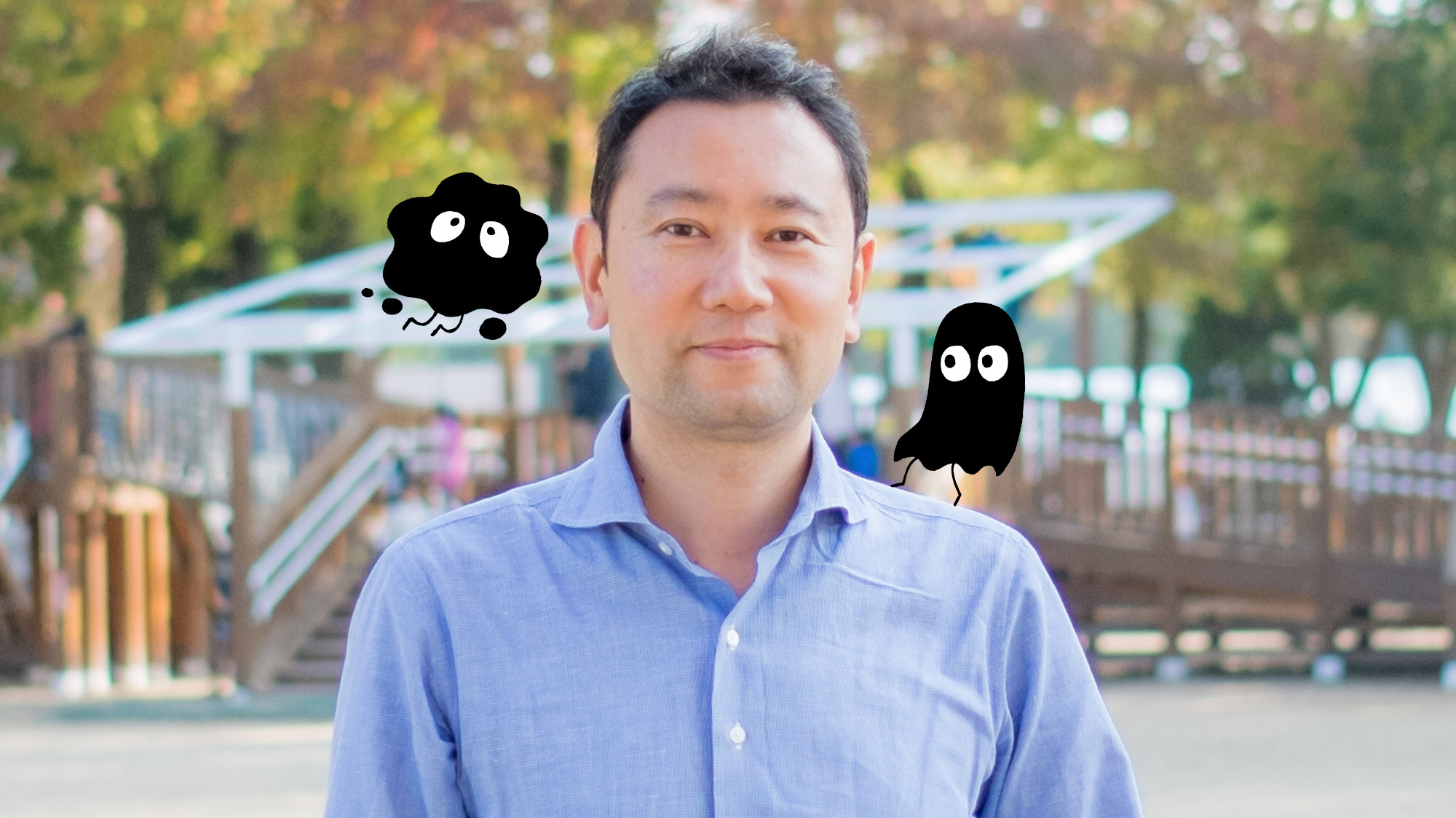
【後編】松村 圭一郎
身体を媒体とした他者との関わりが、自分を変える
自分らしく、他者と共に生きるための文化人類学の教え
2021.09.30
「私」と「あなた」は、何によって分けられているのでしょうか? 肌の色、生まれた国、育った環境……分かつものはたくさんあるようにも思います。しかし、本記事でお話をうかがった松村 圭一郎さんは言います。「他者との違いは、身体を媒体にして交わることでしか、分からない」と。
文化人類学者として豊富なフィールドワークの経験を持つ松村さん。国家が生み出した「固定的なアイデンティティ」という幻想と、「自分」の曖昧さについてのお話を聞いた前編につづき、後編では自分らしく、多様な他者と共に生きていくための方法をうかがいます。ポイントは「自分をひらいておくこと」です。
( POINT! )
- 「ひとつのことをやる」ことが馬鹿にされる社会もある?
- 他者と関わることが、自分の輪郭を揺さぶる
- 大切なのは自分を「ひらき」、変化を受け入れること
- インターネットは、自分を変えない
- 身体を媒体にして、他者と関わることから変化ははじまる
- 「違い」がカテゴリーになっているのではなく、カテゴリーが「違い」を生み出す
- カテゴリーは、人を固定化する

松村 圭一郎
1975年、熊本生まれ。京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有と分配、貧困や開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社)、『基本の30冊 文化人類学』(人文書院)、『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、『はみだしの人類学』(NHK出版)、共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)がある。
日本に根づく「ひとつのことをやる」信仰
さっそくですが、「自分らしく」生きるためにはどんなことが大事だと思いますか?

松村
一つだけの正解はないとは思いますが、「変化を受け入れること」が重要だと考えています。現在の日本では「一つの目標を掲げ、その目標達成に向けて一心不乱に努力すること」がよしとされていますよね。その成功モデルにみんながとらわれすぎているのではないかと思うんです。
たしかに、ビジネスパーソンとしても「とにかく何か一つのことをやり抜くこと」が求められる風潮がありますよね。

松村
そう。「目標やゴールを簡単に変えてしまうこと」は、否定されがちですよね。だけど、世界に目を向けるとそれだけが唯一の成功モデルではないと分かる。私が編集に携わった『働くことの人類学』という本に、人類学者の丸山 淳子さんとの対話が収められています。

働くことの人類学
松村 圭一郎 +コクヨ野外学習センター (編)…

松村
丸山さんはアフリカ南部の狩猟採集民族であるブッシュマンを研究対象としたフィールドワークをされているのですが、ブッシュマンたちは頻繁に仕事を変える人が多いのだそうです。道路建設などの公共事業で働いているときもあれば、狩猟採集生活を送っているときもある。そして、農業とか牧畜とか、一つの仕事だけに専念させようとして開発計画を進める役人たちのことを、馬鹿にするように「ひとつのことをするやつら」と呼んでいるそうです。
ブッシュマンたちにとって「ひとつのことをする」のは、むしろおかしなことなんですね。

松村
日本に生きている私たちの感覚とは逆ですよね。こうした考え方にもとづけば、あきらめたり、途中でやめたりしてしまうことも、ポジティブにとらえられます。「これあきたな」とか「もういやだな」と思う状況になるって、「失敗」ではないんです。選択肢を一つ消せるわけですから。
周りも「その道があなたの道ではないことが分かってよかったね」と、失敗を肯定すべきだと思うんですよ。「自分らしく生きる」ためには、さまざまな選択肢を試しながら、計画通りにいかないこと、予定が変わってしまうことをポジティブに受け入れる必要があると思います。それは「自分らしさ」を固定的にとらえない態度でもあります。
自分という輪郭を揺さぶるために、他者と関わり直す
日本人は昔から「ひとつのことをやる」信仰を持っていたのでしょうか。

松村
いえ、そんなことはないと思います。少なくとも、農業などの一次産業が経済の中心だった時代は、そういった信仰は持っていなかったはず。農業をなりわいとする人のことを、かつて「お百姓さん」と呼びましたが、これは「百の名前を持つ人」、つまり「さまざまな役割を持っている人」という意味です。多くのお百姓さんたちは農業だけではなく、さまざまな「副業」を持っていました。
日本人もかつては「いろんなことをする人」だったと。

松村
しかし、二次産業や三次産業が発展する中で、それは次第に変化していきました。企業や労働市場が「ひとつのことをやる」ように求めて、分業体制を築きてきたわけです。「この人は何ができるのか」把握した方が管理しやすいですからね。何を任せればいいか分かりやすいじゃないですか。高度経済成長の時代などは、「ひとつのことをやる」ことこそが、労働市場において大きな価値になっていた。
しかし、現在のように流動性が高く、予測可能性が極端に低い時代において、その価値は下がりますよね。「ひとつのことしかできない」になってしまう。労働市場の中で求められる力も変化し続けているわけですからね。「ひとつのことをやっていればよい」時代は、ある意味では平和だったんだと思います。
なるほど。


松村
現代はそうした「一歩先に何が起こるのか分からない」時代だからこそ、自分を「ひらいておくこと」が大切だと思います。自分自身の変化を柔軟に受け入れる態度、とでも言いましょうか。私たちは常に自分をひらいたり、とじたりしながら生きています。ときには、それまでつくり上げてきた自分を守るために、誰かの言うことや外部の変化に応じない態度を取ることも大事です。そうすることで、次第に自分という輪郭ができていくわけですから。
しかし、その輪郭はときに自分を縛り、閉じ込める固い殻にもなり得る。自分をとじてばかりいると、次第に変化できなくなり、新しい「自分らしさ」を手に入れる機会を失ってしまう。そうならないために、「他者と関わること」が大事だと思います。
他者と関わり続けることが、新しい自分をつくることにつながる。

松村
自分を変化させるために、本を読んだり、セミナーに行ったりすることも大事ですが、インプットを増やすだけでは自分を変えられません。これまで会ったことのない人に会ったり、行ったことのない場所に行ったりして、他者と関わり直すことが私という輪郭を揺さぶり、新たな変化のきっかけになるんです。
「自分の弁当を、自分で食べる」は当たり前じゃない?
松村さん自身が「輪郭を揺さぶられた」と感じるのはどんなときですか?

松村
フィールドワークをしているときは、常に揺さぶられていますね。大学時代、卒業論文を書くために八重山諸島にある黒島でフィールドワークをしたんですが、そこでの経験はまさに自分を揺さぶるものだったと思います。
たとえば、島の敬老会に出席させてもらったときのこと。おじいちゃんおばあちゃんには昼食用のお弁当が配られるのですが、他の人は自分で弁当を持って行くんです。そして、昼食の時間になって、私はもちろん持参した弁当を食べはじめたのですが、周囲の人がなかなか弁当を食べない。「おや?」と思っていると、みんなが自分の弁当をテーブルの真ん中に置いて、シェアして食べ出した。そうしたお祝いの席などでは、お弁当はみんなでシェアすることが当たり前だったんですよ。
松村さんだけが自分のお弁当をシェアせず、独占してしまったと。


松村
その後「あ、お前あのとき弁当を一人で食べていただろう」とか言われて、恥ずかしい思いをしました(笑)。
そして、その1ヶ月後くらいに石垣島のゲストハウスに泊まることがあったんです。そこで、宿の管理人が一人で缶ビールを持ち出して飲みはじめたとき、「この人、なんでビールをシェアしないんだろう」と思って(笑)。たった1ヶ月前には自分も一人で飲み食いしてしまっていた私が、「一人で飲み食いすること」に違和感を持つようになっていた。
まさに他者と関わることで、自分が変化したわけですね。

松村
「自分が揺さぶられる」ということは、ある意味ではそれまでの自分が否定されることでもある。自分の無知さや浅はかさを突きつけられるわけですよ。それは心地よい経験ではありませんよね。でも、そういった経験からしか成長や変化は生まれません。
もちろん、ある程度周りがその人を肯定してあげることも大切です。しかし、「自分は不十分である」という認識を持つことから、変化ははじまります。そして、そういった認識を与えてくれるのは、いつだって自分とは「ずれ」をもった他者との交わりなんです。
身体を媒体として他者と関わることで、「私」は変化する

松村
他者と直接会い、コミュニケーションを取ることで、他者の考えが私の身体に入り込んでくる。それはつまり、私という輪郭が一時的に溶け出し、他者と混じり合っているということ。身体的な経験こそが、変化をドライブさせるのだと思っています。
ですが、たとえば「黒島ではご飯はみんなでシェアする」という情報は、書籍やインターネットからでも得られると思います。なぜ、直接他者と交わることが重要なのでしょうか。

松村
理由は2つあると思っています。1つ目の理由は、身体を媒体として他者と交わることが「自分をひらく」ことにつながるから。
直接的なコミュニケーションは、常に危険をはらんでいます。直接会っている相手に罵詈雑言を投げかけたりしたら、怒らせる可能性がありますよね。そんな危険があるからこそ、私たちは言葉を選びながら、慎重に他者と言葉を交わしています。恋人関係でも、夫婦関係でも、思ったことをそのまま言ってしまえばその関係はすぐに終わってしまうはず。つまり、どこかで「本音」を抑えて、相手の存在を自分の中に取りこみながらコミュニケーションを取っている。
たしかに。

松村
一方、インターネット上での匿名のコミュニケーションは、他者にどんな言葉を投げかけても、身体的な危害を加えられる可能性はありません。
もちろん、多くの人はそれでも抑制し、言葉を選んでいるとは思います。しかし、直接コミュニケーションを取るときに比べると明らかに危険性は低い。だから、自分の考えをストレートに表現できる。もちろん、そのよさもありますよね。でも、それは「自分をとじる」「自分の殻の中にとどまる」ことにもつながるわけです。
相手の言い分に耳を貸さなくても済む、というか。

松村
そうですね。身体的なコミュニケーションは、「自分をとじておく」だけでは成り立たない。常に相手は何を言いたいのかを考えなければなりませんし、「自分だけが正しい」という前提ではコミュニケーションは進みませんから。
匿名ではない関係で、互いの身体を相手を取りこむ媒体にして他者と交わるからこそ、私たちは「自分をひらく」ことができますし、新たな変化のきっかけになるのだと思っています。
2つ目の理由はどのようなものなのでしょうか?

松村
身体的な経験には「思いもしなかったこと」が付き物だから、です。インターネットでも情報を得ることはできますが、結局は自分が「知りたいこと」を選択していますよね。もちろん、たまたま流れて来たニュースを読む、ということもあるとは思いますが、基本的にはそのニュースを読むか読まないかは自分で選べる。
でも、身体的な経験の場合は、偶然から逃げられない。私の意志や計画に関係なく、思いもしなかった出来事に遭遇するわけですよ。出会いたいかどうかは別にして、常にまだ見ぬ他者と出会う可能性にさらされ続ける。身体がそういった偶然性にさらされているからこそ、「自分をひらき」、輪郭を揺さぶるような機会に出会えるんです。だから、ある意味で「身体」は、もうすでに「ひらいている」わけです。それを頭で概念としてのカテゴリーに閉じ込めてしまっている。
カテゴリーが「違い」を生む
なるほど。でも「自分とは異なる他者」と交わることって、そんな簡単なことではないというか、怖いことでもありますよね。

松村
「自分とは異なる」とはどういうことでしょう?
うーん……そう言われると難しいですね。違う国に暮らす人、とかでしょうか……。

松村
私たちは常に何かしらのカテゴリーにあてはめて、自分や他者を認識しますよね。たとえば、多くのエチオピア人の肌は黒く、私の肌は黒くありません。たしかに見た目では、エチオピアの人びとと私たちは「異なる」わけです。
でも、エチオピアで長くフィールドワークをしていると、エチオピアの人びとの顔が日本の同級生たちのように見えてくることがあるんですよね。たしかに、エチオピアに行く前は「うまくコミュニケーションできるかな」と不安に思っていましたが、行って2週間ほどすればそのへんの床屋の兄ちゃんといっしょにビールを飲むようになったり、おごってもらったり、日本にいたときと変わらない人間関係がそこに生じるわけです。

「異なる他者」のカテゴリーにあった人が、いつの間にか「親しみある」カテゴリーに変わったと。

松村
つまり、差異があってカテゴリーができているのではなく、どんなカテゴリーで他者と関係を持つかによって、そこに「違い」があるように思えたり、あまり「違い」がないように思えてしまう。私たちが認識している人種や肌の色といったカテゴリーは、絶対的な差異ではありません。既存のカテゴリー以外の差異を知るためには、そのカテゴリーがつくる「乗り越えがたい差異」という幻想を越えて、他者と身体をもって交わるしかないんです。
私もエチオピアでフィールドワークをはじめるまでは、エチオピアに生きる人たちを「エチオピア人」として認識していました。ですが、フィールドワークを通じて先ほど言ったような関係を築けたとき、「エチオピア人」だった人が「床屋のムハンマド」になるんですよね。もちろん、私とムハンマドの間には、いくつもの違いがあります。しかし、その違いは決して「肌の色」などで表せるものではないと気付くわけです。
多様な社会をつくるために、「境界」を解きほぐす
既存のカテゴリーを越え、人と人として交わったときにはじめて、自分と他者の違いが分かる。そういった経験が新たな「自分らしさ」に気付くことにもつながりそうですね。

松村
そうですね。一方で、日本の現状を見ていると「多様性が大事」と言いながら、既存のカテゴリーに基づいて境界線を引きすぎてしまい、「自分と違う人」と出会うことが少なくなってしまっているのではないかと。
「マジョリティではない人」が、表に出ることやマジョリティと交わることを阻む社会になっていると感じるんです。たとえば、小学校や中学校には特別支援学級が存在しますよね。私たちは子どものころから、自然と「障がい」のあるなしといったカテゴリーを意識せざる得ない社会に生きている。だからこそ、「自分とは違う人」との付き合い方が分からなくなってしまっているのではないでしょうか。
たしかに。

松村
たとえば、イタリアは、1970年代末から精神科の病院を廃止していきました。日本では"心を病んでいる"とされ、病院に隔離されるような人びとを、「ちょっと変わった近所の人」として地域全体が支えている。エチオピアでも、同じような光景を目にします。
既存のカテゴリーに沿って人を分類することは、ある人をそのカテゴリーの中に「閉じ込めて」しまう危険性があることをもっと認識しなくてはいけないと思っています。"普通ではない"人びとを隔離しながら「ダイバーシティが大事」と言っているだけでは、世の中は変わらないと思います。
[取材・文]鷲尾 諒太郎 [編集]小池 真幸





