
【前編】長内 厚
揺らぐ「正しさ」。不確実性の高い社会で、よりよい選択をするには
経営学者に聞く「多様性」の本当の意味
2025.06.19
「正しさ」とは、いったい何でしょうか。
多様性に配慮することには経済的な合理性がある——そんな共通認識に、逆風が吹いています。環境に配慮したつもりの選択が、別の側面ではかえってマイナスになることも。企業にとっても個人にとっても、「正しさ」が揺らいでいる時代。不安のなかで極端な意見が広まりやすくなっています。
そんな時代にバランスのとれた選択をし、成長を持続するにはどうすればいいでしょう。
「世の中に絶対はない」という姿勢が大切だと語るのは、早稲田大学商学学術院教授の長内厚さん。YouTubeチャンネル「長内の部屋」でも経営の本質をわかりやすく伝えている長内さんに、お話を伺いました。
( POINT! )
- 正しさは時代によって変化
- 正解がないなかで、選択を考える
- ビジネスにはバランス感覚が必要
- 技術だけを追い求めるのは極端な思考
- 高機能製品には丁寧な説明が必要
- 機能的価値と意味的価値
- 文系理系の分断を超える

長内 厚
早稲田大学商学学術院経営管理研究科教授、総務省情報通信審議会専門委員。1997年京都大学経済学部卒業、同年ソニー株式会社入社、薄型テレビ事業立ち上げ、映像関連商品の商品企画、技術企画、プレジデント付商品戦略担当を務めた。2004年筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士前期課程経営システム科学専攻修了、07年京都大学大学院経済学研究科ビジネス科学専攻博士後期課程修了、07年ソニー株式会社退職、同年神戸大学経済経営研究所准教授、11年早稲田大学商学学術院商学研究科准教授、16年より現職。共書に『イノベーション・マネジメント』(中央経済社)他多数、著書に『半導体逆転戦略』(日本経済新聞出版)。
「正しさ」は揺らぐもの。私たちは相対的な世界に生きている
時代や政治の影響で、これまで「よい」とされてきたものがそうではなくなることがあります。「正しさ」って何でしょう?

長内
「正しさ」は、時代によって変化するものですよね。「人の命を大切にする」といったことはある程度普遍的ですが、命の重さについても時代によって変わってしまうことがあります。変化に対応することは必要ですが、新しい事象に合わせることが本当に「変化に対応する」ことかどうかも、考えるべきだと思います。
アメリカの反DEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)の動きにともなって、企業の対応にも混乱が生じています。

長内
そうですね。ダイバーシティはアメリカではシステムや法律で守られるところまで来ていて、それが保守派から見て行き過ぎに見えて揺り戻しが起きているところがあります。でも日本に関していえばシステムが整っていない状態なので、まだまだSDGsもダイバーシティも推進しなきゃいけない状況。時代だけでなく、地域による変化もありますね。
SDGsの推進で社会から評価され利益にもつながるという考え方はシンプルですが、補助金などの後押しがなく経済的合理性が得られないとなると、揺らぎが生じますよね。

長内
元々揺らぐものだと思うんです。ビジネススクールでは学生にディスカッションをしてもらいますが、答えが必ずしも1つにならない「意思決定問題」を取り扱います。AとBそれぞれにメリットとデメリットがあるなかでよりましな選択をするために役立つものは、日頃の経営の選択。「絶対的に正しい」「絶対的によい」というものはなく、そのなかで選択していくことを考える必要があります。
たとえばEV(電気自動車)は環境によいと言われていますが、廃棄バッテリーなどまだ解決できてない問題があります。一方で内燃機関(ガソリンエンジンなど)は悪いと言われていますが、日本メーカーが燃費のよい内燃機関を作ることは、どこかが粗悪な内燃機関を作り続けることより悪ではないかもしれませんよね。でも「内燃機関は悪」としてしまうと、ハイブリッドを作ってるメーカーも燃費のよいエンジンを作ってるメーカーもひっくるめて悪になってしまう。それは極端な発想で、社会のなかで矛盾が生じてしまいます。
私たちは相対性のなかで生きているので、絶対的な正しさを追い求めることには元々無理があります。それが最近特に際立って矛盾が多く見えるようになってきているので、「世の中に絶対はない」という本質的な問題について、より考えなきゃいけない局面に来ていると思います。

「高い技術さえあればいい」も極端な考え方
「答えがない時代」と言われていますよね。

長内
不確実性が高くなって意思決定問題みたいな課題に直面することが増えていますが、元々あったものではあります。ただ昔はみなで同じ方向に進もうという共通認識が多かったので、相対的な意思決定もしやすかった。今は様々な意見や極端な意見が出ることでバランスを取りにくいので、問題の本質が見えにくくなっている状況があると思います。
迷える人たちが多いなか極端な意見が広まりやすい背景には、SNSを含めたアテンション・エコノミーもあります。個人の選択に大きな影響を与えていますが、装置産業などの大きな産業にも影響があるでしょうか?

長内
企業経営者はバランスを取っていく人たちなので、あまり極端なところには影響されていないと思います。たとえば台湾にTSMC(*1)という半導体の企業があります。アメリカからの圧力でアリゾナに工場を作りましたが、すべてそちらでというわけではありません。最先端のところは台湾に残して、先端だけど最先端ではないものをアリゾナに出しているんですよね。その辺のバランス感はビジネスにとっては非常に重要なんですが、日本企業の経営者はわりと極端に走りがちなところがあります。
そうなんですか?

長内
特に日本のエレクトロニクス産業は、戦略的なバランスより技術だけを追い求めるといった、一方向でものを考える傾向があるんですね。
日本の家電って、たとえば電子レンジがやたら多機能だったり説明書が長かったりしますよね。極論より中庸を取っている印象があるんですが。

長内
日本のメーカーは数を追わずに高い技術で差をつけた商品を作りがちですが、市場では価格と機能のバランスを取れたものが求められていたりします。電子レンジに機能がいっぱいついてるのも、「機能が多いのはよいこと」「技術的な成果を示すことが大事」と考えている結果なんですね。
機能がたくさんあると説明書も長くなるし、商品がわかりにくくなります。でも、ネットや量販店では説明を介さずに売ることが当たり前に。流通サイドのサポートはないのに、丁寧な説明が必要な製品を作るということをやっています。
Appleはその逆で、自分たちでは生産をしていません。生産は委託するけれど流通だけはApple Storeで行い、新しく出てきた機能や世界観を直接伝えるというバランス感覚を持っているんですよね。

「正解のない時代」にこそ求められる多様性
日本のメーカーは「伝え方が下手」だとよく聞きます。

長内
製品の価値は大きく分けると、数字や言葉で表せるような「機能的価値」と情緒とか感性みたいな「意味的価値」があります。日本企業は機能的価値に極端にフォーカスしがちですが、Appleは意味的価値の重要性をすごく認識してるんですよね。
スターバックスも意味的価値が高いビジネスですが、「スタバでMacを使ってるとかっこいい」といった価値をうまく作っています。その辺りも意味と機能のバランスを整えてるところ。テクノロジーの会社のように見えて、テックだけじゃないところがAppleの強さという気がしますよね。
「iPhoneじゃないと高校で使い辛い」という投稿をSNSで見ることがあります。そういう空気観を日本企業が作れなかったということでもありますが、漫画やアニメ・ゲームでは世界観を創って広めることができていますよね。なぜそういうことが起きるんでしょう。

長内
日本社会では、アートの世界とサイエンスの世界が完全に分離しています。コンテンツ産業はアートのもので、エレクトロニクスとか自動車のようなテクノロジー産業はサイエンスの話。その2つがもう少し近いものになるとAppleのように様々な世界観を技術と統合することができそうですが、文系・理系の壁が非常に厚く、分断が起きているのかなという気がします。
文系・理系の壁があることで、思考の偏りも生まれますよね。

長内
その垣根は本来はなかったもので、文系・理系と分けることで人為的に分断が生まれてしまったのだと思います。
10年ほど前、理系の博士号を持った方をビジネススクールで指導したことがあります。その方は「文系と理系はまったく異なる世界だと思っていたけれど、経営学の修士論文を書くなかで、両者に通じるものが多いと気づいた」と言っていました。
私のゼミには理系出身の人もいれば文系出身の人もいますし、社会人として実務を続けながら学んでいる人も多いです。たとえば広告代理店で伝統工芸のプロジェクトに関わっている人や、VRのエンジニア、トイレの研究者など、多彩なバックグラウンドの人たちが一緒に学んでいます。
みなさん「いろんな出自の人がいて本当によかった」と言いますし、私自身も多様な視点が集まることで生まれる力を実感しています。そうした多様性こそが、「正解のない時代」を生き抜く企業の力になると考えています。
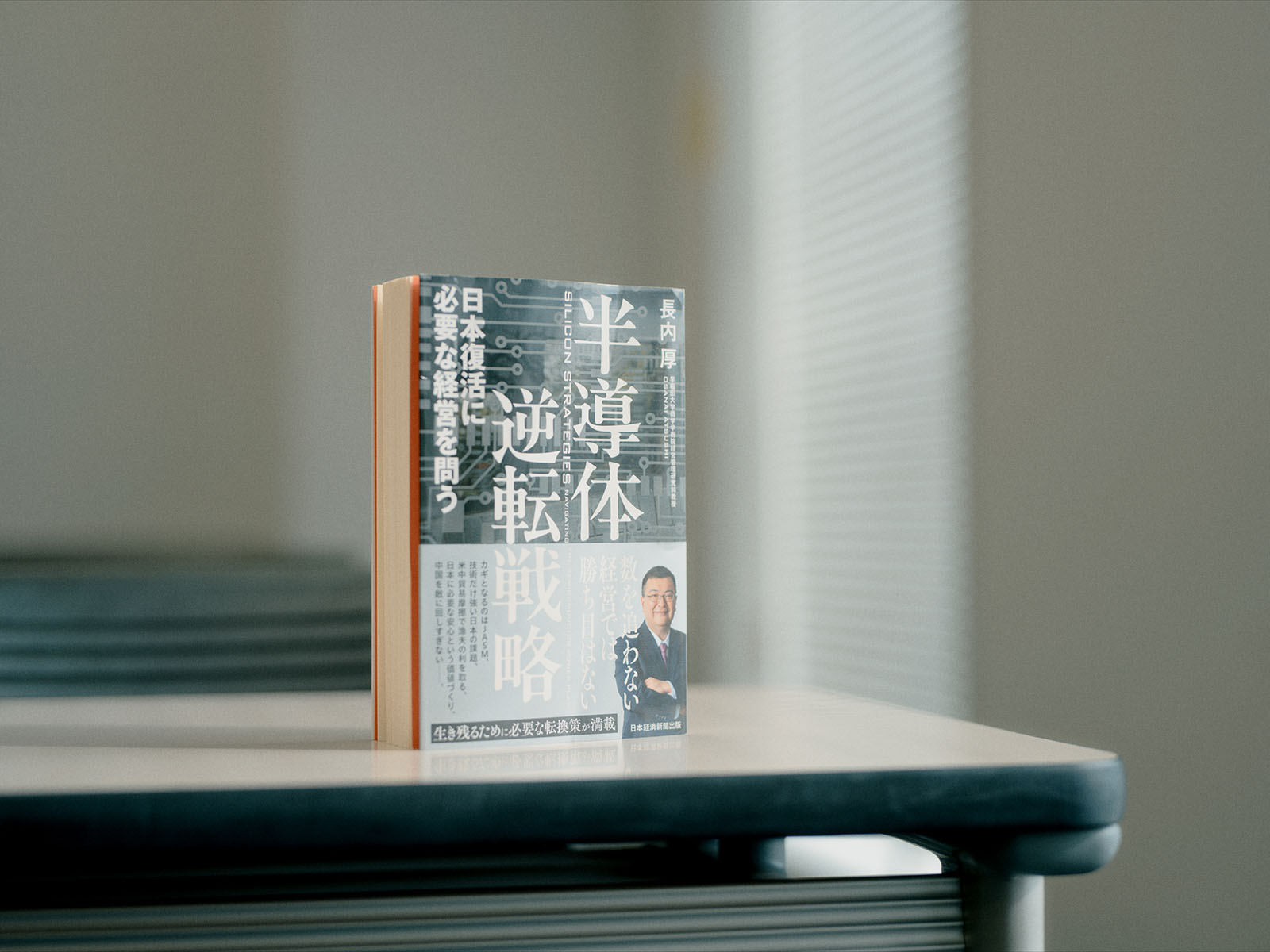
多様性に逆風が吹き極端な思考になりがちな今だからこそ、幅広い視野が必要だと伺った前編はここまで。後編では、実際に分断を乗り越え、非効率ともいえる多様性を維持するには?を深掘りします。お楽しみに。
- ※1:
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company。台湾に本社を置く世界最大の半導体ファウンドリ(他社設計の半導体を製造する)企業。
[取材・文]樋口 かおる [撮影]野間元 拓樹






