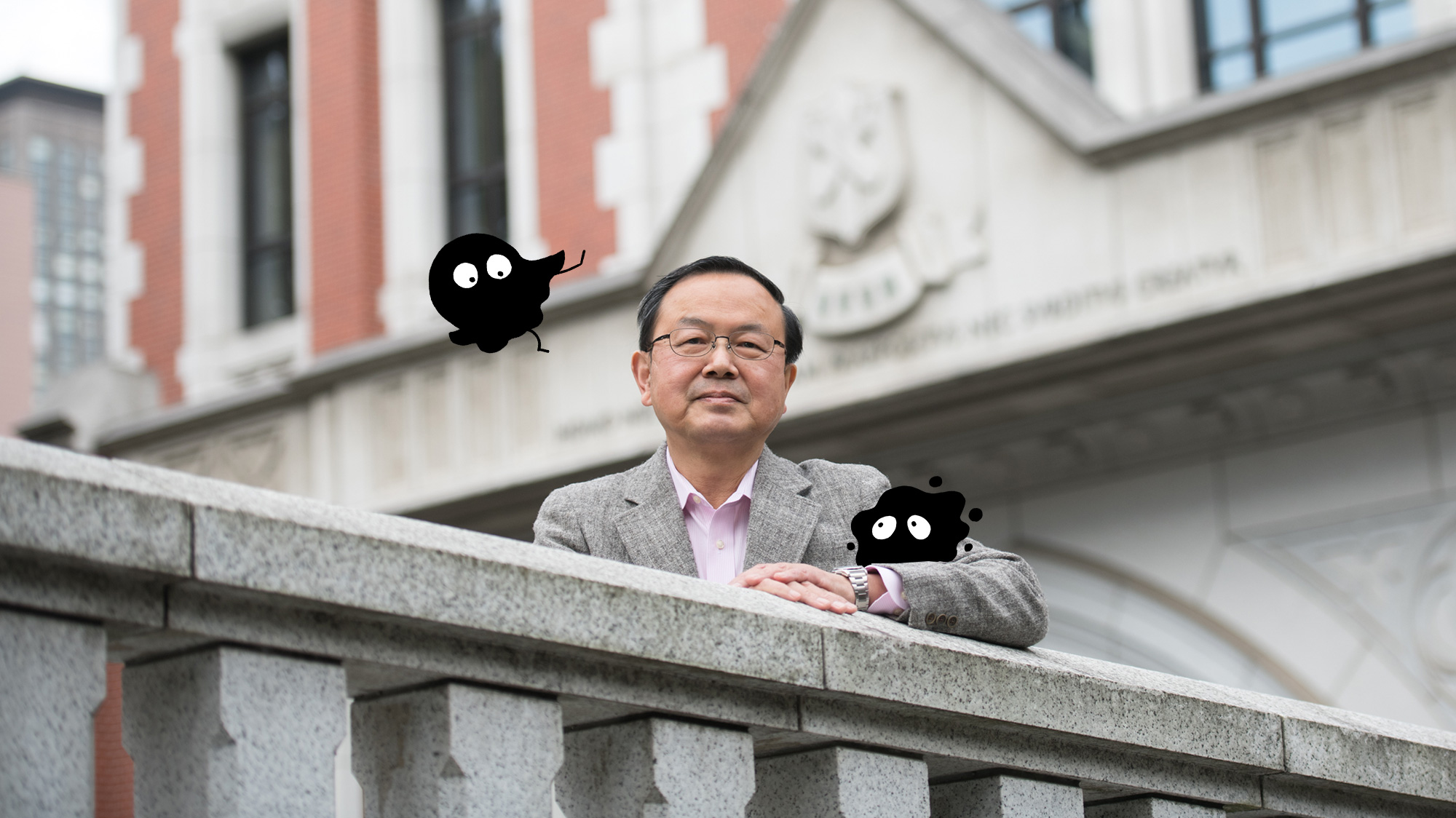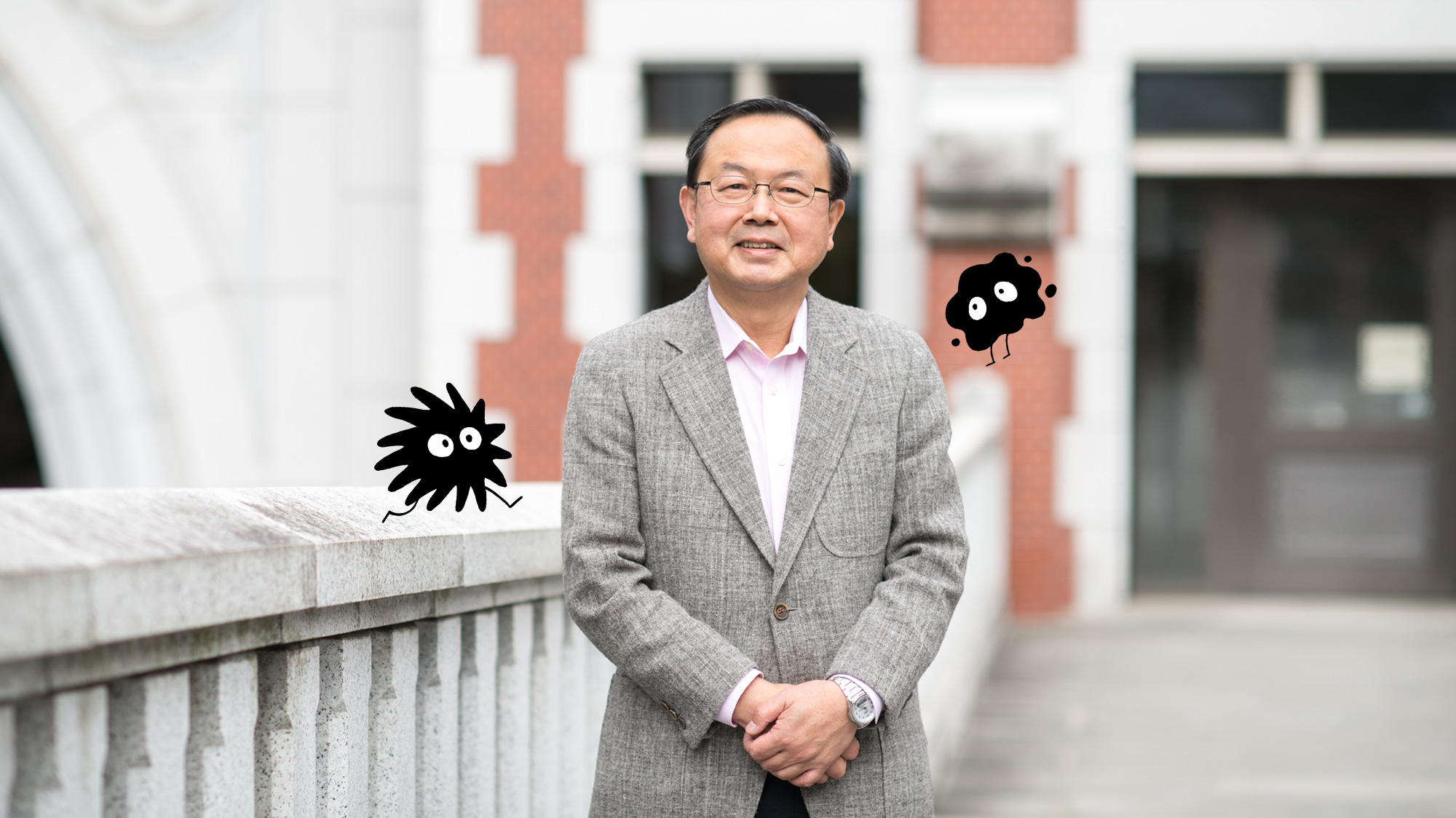
【前編】山内 志朗
私たちは、いつから「自分とは」と考えるようになったの?
哲学者が語る、「私」をめぐる問いの歴史
2022.03.17
『うにくえ』ではたびたび「自分とは」「自分らしさとは」という問いについて取り上げてきました。まあ、メディアのテーマなので当たり前ですし、これからもこれらの問いについて考えていこうと思っているのですが、ある日、はたと思いました。「待てよ。そもそも、『自分とは』と考え出したのは、誰なんだ?」と。
生物学上の「人類とは」という問題はさておき、何万年も前から、私たち人類は「自分とは」と悩み続けているのでしょうか? はたまた、もうちょっと後から?
「自分とは」という問いの歴史を知ることで、その答えに対する示唆を得られるかもしれない。そんなやや無茶振りとも思える要望に応えてくれたのは、哲学や倫理学の研究者である山内 志朗さんです。
私たちのご先祖さまが「自分とは」という問題を考えるようになったのは、約800年前だと考えられると、山内さんは言います。なぜ、私たちはこのやっかいな問いに向き合うようになったのでしょうか。いつもより、ちょっとだけ難しい話になるかもしれませんが、ぜひ大学の講義を聞いているような気分で読んでみてくださいね。
( POINT! )
- 「自分とは」という問いが発生したのは、13世紀のヨーロッパ?
- ヨーロッパがイスラム文化と出会い、「個人」をめぐる問題が生まれた
- 「モノをどうとらえているのか」という問題が、「私とは」という問いにつながった
- 「足し算」では、個体は特定できない
- 経済と教会も、中世ヨーロッパに「個人」の問題を生んだ要因
- 日本に「個人」という概念が根付きづらいのは、「城壁」と「世間」の影響?

山内 志朗
1957年、山形県生まれ。慶應義塾大学文学部教授。
東京大学大学院博士課程単位取得退学。新潟大学人文学部教授を経て、現職。専門は中世哲学、倫理学。その他、現代思想、修験道など幅広く研究・執筆活動を行う。著書に『ぎりぎり合格への論文マニュアル』(平凡社新書)、『普遍論争——近代の源流としての』(平凡社ライブラリー)、『目的なき人生を生きる』(角川新書)、『自分探しの倫理学』(トランスビュー)、『わからないまま考える』 (文藝春秋)、編著に『世界哲学史』シリーズ(ちくま新書)ほか。
「私とは」という問いの起源は、中世ヨーロッパ?
「自分とは」という問いをたくさん考えてきたのは、哲学者なんじゃないかと思いまして。だから今日は、哲学の研究者である山内さんに、哲学者たちが「自分」をどうとらえてきたのか教えてもらいたいと思っています。

山内
実は、古典的な哲学では「自分とは何か」という問いについてはあまり取り上げられていないんです。
ちょっと意外ですね。哲学って大昔から「自分とは」といった抽象的なテーマを取り扱う学問だと思っていたので。

山内
抽象的なテーマといっても、古典的な哲学で主流なのは「存在とは」「真理とは」「真実とは」といった問いを取り扱うこと。哲学者たちがより直接的に「個人」とか「私」について考えるようになったのは、13世紀ごろ、ヨーロッパにおいてだったと言われています。
なぜ、そのころのヨーロッパの哲学者たちは「自分とは」と考えるようになったのでしょう?


山内
要因はいろいろあると思いますが、最も影響が大きいのはイスラム文化がヨーロッパに流れ込み始めたことだと考えています。
イスラム文化がきっかけで、ヨーロッパの人々は「私とは」と考え始めた?

山内
はい。このことを理解するには、ヨーロッパの人たちが人間という存在をどう理解していたか、から説明しなければなりません。ちょっと面倒くさい話になるかもしれませんが、大事な話なので。
まず、ヨーロッパにおいて人々のさまざまなことに対する考え方のベースになっているのは、キリスト教の教えです。では、そのキリスト教的な世界の見方が何に立脚していたかと言えば、もちろん他のものからも影響は受けているのですが、古代ギリシャの哲学者・アリストテレスの思想の影響が大きい。
アリストテレスが、どんな風に人間をとらえていたか。かなり単純化してしまえば、彼は「感性」と「知性」をわけて考えていました。
感性と知性。なんだか難しそうな話です……。

山内
ゆっくりいきましょう(笑)。感性とは、視覚、触覚などの五感を通して何かを感じる力のようなもの。対して、知性とは五感を経ずに何かをとらえる力のようなものだと考えてください。そして、人は感性によって「個体」をとらえ、知性によって「普遍」、つまりはすべてのものに共通する概念をとらえると考えていた。
私たちは手や耳によって、他の誰かや生き物、モノなどを認識して、知性によって「人間とは〇〇である」といった共通概念を知る、みたいなことですか?

山内
そういうことです。アリストテレスは、感性は普遍に触れられないし、知性は個体に直接触れられないと考えていたわけですね。でも、13世紀ごろに「それってほんとにそうか?」と言われるようになった。そのきっかけが、イスラム圏の文化の流入なんです。
「このりんごは、世界にたった一つのりんごである」と証明できるか
イスラム圏では、知性と感性に対する考え方がヨーロッパと違ったということですか?

山内
はい。イスラム圏では、知性そのものが物質をとらえると考えられていたんです。人間は知性によって個体をとらえていると。このことをわかりやすく説明すると、たとえば絵画を鑑賞するとき、私たちはもちろん目で絵画を観るわけですが、同時に知性でも見ている。
どういうことかと言うと、たとえば美術史を勉強して、その絵が描かれた時代背景や、その絵を描いた画家のことを勉強すると、絵の見方が変わるじゃないですか。あるいは、私たちが食事をする場所を選ぶとき、食べログなどで情報を得てから、そのお店で食事をすると、味覚という感覚以外の要素も、感じ取る味に影響を及ぼしている可能性もある。
「ここ、食べログの星4なんだよ」と言われたら、おいしく感じちゃいます(笑)。

山内
つまり、感性と知性をきれいにわけることはできないのではないか、というのがイスラムの考え方なんですよね。そういった考え方が13世紀のヨーロッパに入り込み、議論が巻き起こったわけです。
ヨーロッパで一般的だった、アリストテレス的な物事のとらえ方に疑問が生じ始めたと。それが、どう「私とは」という問いにつながるのでしょう?

山内
「私たちは、どう物事を認識しているのか」という問いが生じる中で、「じゃあ、『個体』ってなんだ?」という問いが生まれたわけです。つまり、感性や知性によって、私たちは「何」をとらえているのか、と。
これまた難しそうな話に……(笑)。


山内
そう身構えないでください(笑)。先ほど、普遍という言葉を使いました。モノから普遍を取り出すにはどうしたらいいかというと、抽象化していけばいいわけですよね。
たとえば、ここにたくさんのりんごがあるとします。そのりんごは、青森県や長野県、山梨県で採れたもので、収穫された時期もバラバラで、それぞれ違う個体なわけですね。でも、収穫時期も問わず、産地も問わなければ、みんな同じ「りんご」になる。これが抽象化するということです。
では、逆に「りんご」を個体化するにはどうしたらよいでしょうか?
産地や収穫時期を足していく?

山内
そのとおり。でも、どこまで足していけば「そのもの」をとらえられるかと言うと、これが難しい。産地を足し、収穫時期を足したところで、当然同じ場所の同じ時期に採れたりんごはたくさんある。どこまで何を足していっても、たった一つの「そのもの」にすることは困難なんです。このことに、13世紀のヨーロッパの人々は気付くことになったわけですね。そして、「私ってなんなのだろう」と考えることになった。
経済システムと教会の変化も、個人を生んだ
イスラムの文化が、「自分とは?」という問いが生み出される大きな要因だったのですね。

山内
ただそれだけでなく、ヨーロッパでの経済システムの変化も影響していると思います。経済の面から説明すると、13世紀にモンゴル帝国がその勢力を拡大したことによって、東アジアからヨーロッパにまたがる貿易ルートが出来上がりました。これによって、経済システムや金融システムを変化させなければならなくなった。
現金の代わりに手形などによって取引を行う為替の仕組みや、銀行のシステムを構築する必要が生まれたわけです。その中で、契約の主体とは何なのか、という問題が立ち上がった。ある人に銀行がお金を貸すとき、借りるのはその人の家なのか、あるいは街なのか……と議論されたかどうかはわかりませんが、結局は「借りるのは、その人『個人』だろうよ」となったわけですね。
経済システムが変わっていくなかで「個人」を特定する必要が出てきた、ということですね。

山内
それから、教会という存在の変化も大きかったでしょう。中世までヨーロッパの人々の考え方の基盤となっていたのは、キリスト教です。当然、その教えを伝える教会という存在が大きな力を持っていたわけですが、1215年に当時の教皇が「告解制度」を制定したんです。
これがどんな制度かというと、キリスト教徒に年1回、教会で自分が犯した罪を告白して、ゆるしを得ることを義務付けたもの。これによって、人々は「『私』の罪」を意識するようになり、個人という概念がつくり上げられた、なんてことが言われていますね。
さまざまな要素が組み合わさり「個人」という概念が生まれ、人々が「私とは」という問題を考えるようになったと。

山内
そうですね。ただ、これはあくまでもヨーロッパの話。イスラムにはイスラムの考え方があるし、東洋に目を向ければ、まったく別の考え方がある。だから、いろんな目線で一つの問題を考えることが重要だと思いますね。
もちろん、さまざまな哲学的な問題を考えるにあたって、起源を知ることは大事なことです。だから、古代ギリシャからの流れを押さえる必要がある。そして、その後ヨーロッパでどんなことが起こり、なぜその問題が取り上げられるようになったかを知ることは重要ですが、それがすべてではありません。
日本に個人主義が根付きづらいのは、「城壁」と「世間」が理由?
これまでにうかがってきた流れでヨーロッパで生まれた「個人」という考えは、なぜ日本にはなじまなかったのでしょうか? 一般論として「日本には個人主義的な考えはなじまない」と言われているかと思うのですが。

山内
まず考えられるのはヨーロッパと日本における街のつくり方、具体的に言えば、お城の違いです。
ヨーロッパの街は、城壁に囲まれていました。つまり、街の中心にお城があって、その城下町や田畑も含めて、ぐるりと壁に囲まれていたんです。なぜ、そういったつくりになっているかというと、富がある場所は略奪の対象になるから。略奪行為から街を守るために、最低高さ5メートルほどの壁を築いていたんです。
対して、日本の城下町は壁の外にあった。城壁はあったのですが、それは城を守るためのもので、街を守るものではなかったわけですね。このことが、日本人のキャラクターを形成する上で影響を与えたのではないかと。「外」と「中」を隔てる感覚が薄かったのではないかと思うんです。
自らが住んでいる街を「自分」、その外部を「他者」に見立てるとわかりやすいかもしれません。日本人は、「自分」と「他者」を隔てる壁がない環境で生きてきたわけです。それが、「個人」という概念を根付かせにくくした一つの要因ではないかと考えています。
なるほど。


山内
それから、「世間」の存在も大きいでしょう。ヨーロッパにも世間という概念がないわけではありませんし、特に中世までは人々の思考に大きな影響を及ぼしていたと考えられています。しかし、16世紀に「主権」「領土」「国民」の三要素からなる、主権国家体制が確立されたことをきっかけに、「世間」という存在は薄れていく。
主権国家は国民一人ひとりが、国家と契約を交わすことによって成立します。つまり、国家と国民が直接結びつくことになり、その中間的な存在としての「世間」が失われたわけですね。
対して、現代に至っても、日本には「世間」が根強く存在し続けている。もちろん、現在の日本は国民が主権を持つ主権国家です。それでも「世間」が残っていることにはさまざまな理由があると思いますが、いずれにせよ、親が子どもに「人様が見ているから」と注意したり、「誰かの目」を気にして行動を変えたりする私たちが「世間」を意識していることは間違いないでしょう。
「外」と「中」を隔てる感覚と、「世間」の存在によって、個人として直接的に国家と結びついている感覚を持ちづらいことが、日本に個人主義的な考えが根付きにくい理由なのではないでしょうか。
「自分とは」という問いの歴史をうかがった前編はここまで。後編ではいよいよ、哲学の見地から「自分とは」という問いに対する、一つの答えに迫っていきます。ヒントは、前編でも取り上げた「個体化」に関する議論。山内さんは、「いくら情報を積み重ねても、『自分』は見つからない。『自分』は引き算の末にある」と言います。後編もぜひお楽しみに!
[取材・文]鷲尾 諒太郎 [撮影]須古 恵 [編集]小池 真幸