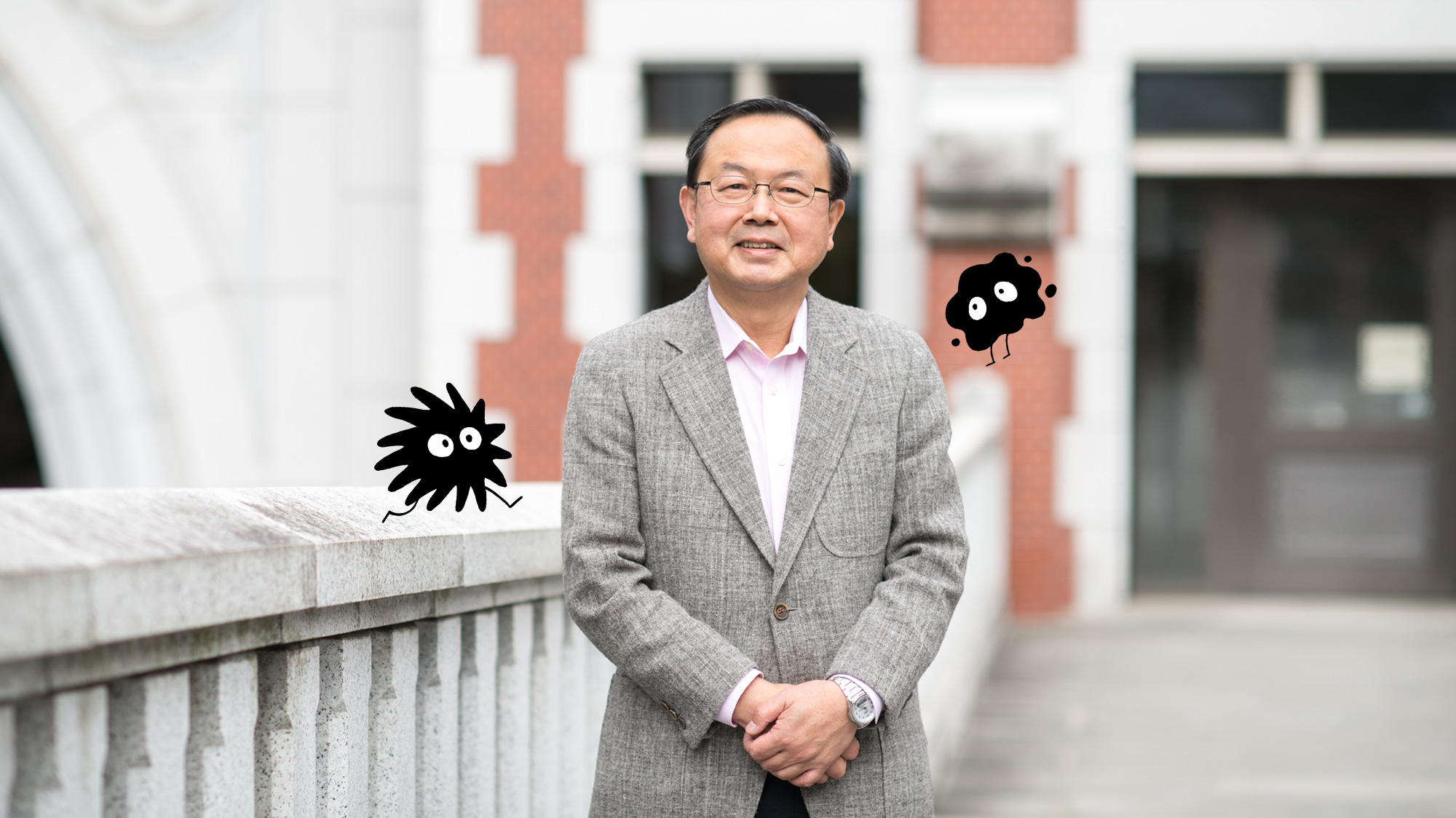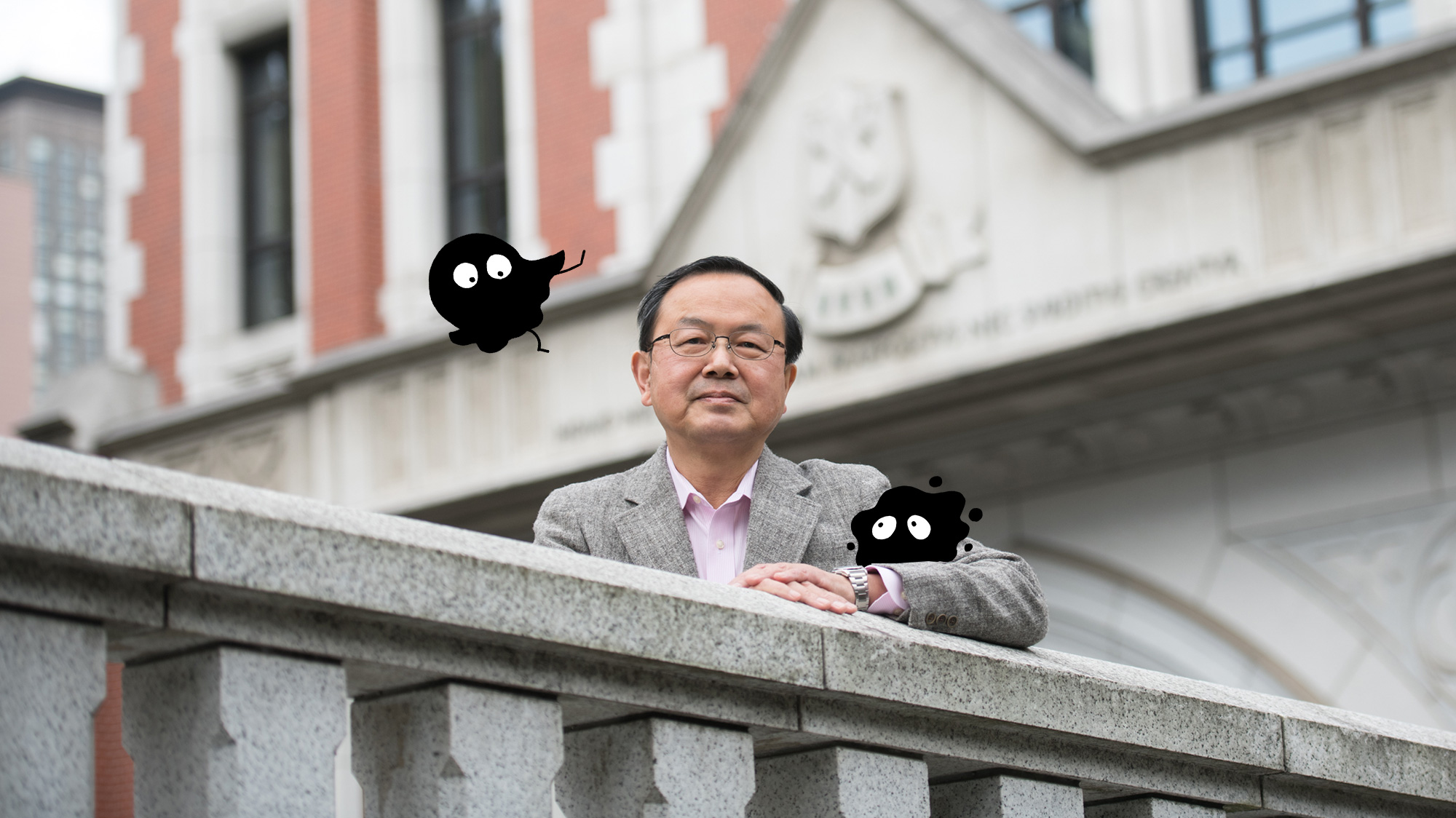
【後編】山内 志朗
結局、「私」って何なんですか?
哲学者と紐解く、私たちが「自分探し」を続ける理由
2022.03.24
さまざまな角度から「個性とは」「自分らしさとは」といった問いを考えてきた『うにくえ』ですが、本記事ではこの疑問に真正面からぶつかってみたいと思います。
一緒に考えてくれたのは、哲学の研究者である山内 志朗さんです。「私とは」という問いの歴史をうかがった前編に続き、後編ではいよいよその問いの一つの答えに迫っていきたいと思います。
山内さんは言います。「『私』とは器であり、ハビトゥスであり、結び目である」と。現時点では「何がなんだか……」ですよね? もう少し具体的に言えば、「『私』とは、さまざまな属性や性質などを盛り込むためのどんぶりであり、無意識での行動や認知などを傾向づける構造であり、人と人との関係性の中に生まれるもの」なのです。
まだちょっとわかりにくいかもしれません。「なぜそう言えるか」もこれだけではわからないですよね? でも、大丈夫。この記事を読み終わるころには、きっと「私」に対する解像度も、「自分らしさ」に対する理解度も、ぐぐっと高まっているはず。
( POINT! )
- 一般名詞の「足し算」では、「私」はとらえられない
- 「私」とは、さまざまなものを盛り込む器である
- 日常生活の中での認知や行動、物事に対する評価を規定する「ハビトゥス」
- 「人間はさまざまな関係の結び目だ」
- 若いころは、器に盛り込める「メニュー」を知らない
- 「自分探し」とは、メニューづくりである
- 「私ならざるもの」とふれ合うことで、「私」を知る
- 「自分らしさ」とは、「好み」のこと

山内 志朗
1957年、山形県生まれ。慶應義塾大学文学部教授。
東京大学大学院博士課程単位取得退学。新潟大学人文学部教授を経て、現職。専門は中世哲学、倫理学。その他、現代思想、修験道など幅広く研究・執筆活動を行う。著書に『ぎりぎり合格への論文マニュアル』(平凡社新書)、『普遍論争——近代の源流としての』(平凡社ライブラリー)、『目的なき人生を生きる』(角川新書)、『自分探しの倫理学』(トランスビュー)、『わからないまま考える』 (文藝春秋)、編著に『世界哲学史』シリーズ(ちくま新書)ほか。
「私」は、引き算の先にいる
前編では「自分とは」という問いをめぐる歴史をうかがいました。後編では、さまざまな哲学者の思想を研究してきた山内さんといっしょに、その問いについて考えてみたいと思っています。

山内
私は「私とは器である」と考えています。どんぶりのようなイメージですね。前編でりんごを例に、何かしらの属性を足していくことによって唯一無二の個体を特定するのは難しいというお話をしました。
りんごに「青森産」「収穫時期はいつ」などの要素をいくら足していっても、世界で唯一であるはずの「このりんごそのもの」にはならないといった話でしたね。

山内
人間についても、同じことが言えると思うんです。たとえば、私は「山形県出身の」「慶應義塾大学に籍を置く」「哲学の研究者」ですが、歴史をたどればそういった要素を持つ方は他にもいたかもしれない。このことを言い換えれば、いずれも「私」を示す本質的な要素ではない、と言えると思います。
つまり、「学校の先生」や「会社員」といった一般名詞の積み重ねを、どれだけ繰り返しても「たった一人の私」にはたどり着かないわけですね。では、「私とは何か」というと、それらの一般名詞を“盛り付ける”器のようなものだと言えるのではないかと思うのです。
すると、「私」を考えるとき“盛り付けられたもの”に目が行きがちですが、それでは「私」は理解できない?


山内
そう思います。「私」という器は、さまざまなものを受け入れられると同時に、受け入れるものを選んだり、入れ替えたりできる。たとえば、あなたがある大学に入学することを目標にしたとして、その目標を達成したとしましょう。「あなた」という器には、「〇〇大生」という要素が盛り込まれることになります。
やがて、大学を卒業するとその要素は取り除かれることになる。そして、かねてから希望していた会社に入社し、「〇〇社勤務」という要素を盛り込む。そんな風に、器の中のものは出たり入ったりするわけです。
私たちは生まれた瞬間から、私という器の中にさまざまなものを盛り込んだり、取り除いたりしている。器の中にあるものは、あくまでも一時的にそこにあるものでしかなく、移ろうものなんです。それをいくら足し上げても「私」にはならない。そうではなくて、盛り込まれた要素を取り除いていった先に、「私」は表れるのだと思います。つまり、引き算の先に、個体性は発見される。さまざまな要素を足していき、「私」の完成を目指すのではなく、「私」は器として常にそこにあるんです。
「私」は器であり、ハビトゥスであり、結び目である
なるほど。

山内
しかし、「私とは、器である」だけでは「私」の一側面しかとらえられていないと考えています。より正確に「私とは」という問いに答えるために、私は「ハビトゥス」という言葉を使っています。「私とは、器であり、ハビトゥスである」ということですね。
聞き慣れない言葉が……。

山内
補足が必要ですね。ハビトゥスとは、中世哲学で盛んに用いられ、フランスの社会学者であるブルデューが復活させた概念で「日常生活の中での認知や行動、物事に対する評価などに表れる傾向であると同時に、その傾向を生み出す構造」だととらえてください。ハビトゥスは「身体化された必然」であるとされています。つまり、生まれた瞬間から、日常生活を送る中で無意識のうちに獲得していくものなんですね。
「なんとなく、これが好きだな」とか「よくわかんないけど、こうしたい」と思うことや、そういった気持ちを生み出すもの、みたいな感じでしょうか。

山内
そうですね。「無意識のうちに所有している、習慣的に発揮できる能力」と言い換えてもいいかもしれません。「マラソンランナー」と言われている人について考えてみましょう。マラソンランナーたちは、常にマラソンを走っているわけではありません。立ち止まっているときもあるし、歩いている時間もあるけれど、「マラソンランナー」と呼ばれるわけです。
それがなぜかと言えば、その人がマラソンを走る能力を備えているからですよね。やや回りくどい言い方をするならば、「その人がマラソンを走ろうと思えば、走りきれる能力を潜在的に備えている」から、その人はマラソンランナーなんです。
「マラソンを走れること」が、ある個人をマラソンランナー足らしめていると。

山内
そのとおり。つまり、私たちはハビトゥスによって「何者であるか」を規定されているわけですね。生まれた瞬間からいまこの瞬間までの間に獲得してきたハビトゥスこそが、「私」なのだと言えると思います。
だからこそ「私とは、器であり、ハビトゥスである」なんですね。


山内
ただし、その定義だと「人との関わり」という観点が抜け落ちてしまいます。「私」は他者との交わりなしに成立しませんから、器とハビトゥスだけでは不十分なような気がしていて。そこで、私がよく引用しているのが、フランスの作家・サン=テグジュペリが『戦う操縦士』の中で書いた「人間はさまざまな関係の結び目だ」という言葉。
「人」が先にあるのではなく、糸と糸が交わったその結び目が「人」になる。そして、その結び目は一回できたら終わりではなく、いつしか解けるかもしれないし、異なる糸と交わって新たな結び目をつくるかもしれない。先ほどの器のお話に寄せて言えば、糸が複数の結び目をつくることによって網のようになり、それが器になっていくイメージを持っています。
「自分探し」は、メニューづくり
「自分探し」という言葉がありますよね。「器であり、ハビトゥスであり、結び目である」という定義にのっとれば、「私」は常にここにある、ということになりますよね。それでも、私たちは「私」を探し続けているように思います。なぜ、私たちは「自分探し」をするのでしょうか?

山内
自分探しとは、メニューづくりなんだと思います。私たちは、器に何を盛り込むかを考え続けているわけですが、特に若いころって「そもそも、何を盛り込めるのか」が分からないわけですよね。それはなぜかと言うと、知っている選択肢、つまりメニューが少ないからなんですよ。
そば屋さんにたとえるならば、「好きなものを食べていいよ」と言われて渡されたメニューに「ざるそば」と「もりそば」しか書かれていないような感じですかね。
「好きなものをって言われましても……」って感じですね(笑)。

山内
そうでしょ?(笑) そして、そのメニューはさまざまなことを経験し、知ることによって段々と増えていく。また、自ら「これはいらないかな」「これは必要だな」と消したり、追加したりすることもできるわけです。
「自分探し」というのは、メニューを見通したり、そのラインナップを考えるような行為だと思うんです。前編では、「自分とは」という問いは中世ヨーロッパで生まれたのではないかというお話をしましたが、中世の「自分探し」は今ほど大変ではなかったのではないかと想像しています。
なぜなら、今より職業などの選択肢が圧倒的に少ないから。見通すべきメニューの数がそもそも少なかった。でも、現代はそうじゃないですよね。職業選択にしても、無限の選択肢があるわけなので「そもそも、どんな選択肢があるのか」を知るだけでも、多くの時間を要します。そう考えると、若者たちが「自分探し」に勤しむ理由も理解できますよね。
なるほど。自分探しと言うと、「どこかにいる本当の自分」を探しているイメージがありますが、そうではなくて「自分という器に何を盛り込むのか」を探っているんだと。そう言われると、いまも“自分探し”の途中なのかもしれませんね。


山内
かつては「“いい大学”に入り、歴史のある規模の大きな会社に就職する」ことが、“正しい道”とされていましたよね。でも、いまはそんな“正しさ”もなくなってしまった。
不確実であいまいな社会の中では、中間領域、つまり自分にとっての「正解」と「不正解」の間にある領域を歩き続けなければならない。このことが、「自分探し」として表れているのではないかと感じています。
そして、やがて私たちは「自分探し」を通して、好みのテイストを見つけていくのだと思います。「そばはこうやってつくらないと」と他者から言われることでメニューに加えるそばの味を決める方法もあると思いますが、「いや、私はその味が嫌いなんだ」と拒否することもできる。そうやって、メニューに加えるものや、その味を自ら判断する力をつけることを通じて、私たちは「確固たる自分」を形づくっていくのではないでしょうか。
「私ではない何か」との出会いを通じて、「私」を知る
ぼくが大学生のとき、「自分探し」のために海外、主にインドに旅立つ友人が少なくなかったのですが「なんでインドなんだろうな」と思っていたんですよ。山内さんのお話をうかがっていると、インドはもとより、海外に行かなくても「自分探し」はできるのではないかと思ったのですが。

山内
もちろん、インドに行かなくてもいいと思いますよ(笑)。でも、やっぱり自分の知らない世界にふれることは大事ですよね。そういった世界にふれたとき、自分がどう感じるのか、どんな反応をするのかを知ることで、「自分という器がどんな形をしているのか」を考えるきっかけになりますから。
かつての日本にも、若者が「知らない世界」にふれるためのさまざまな儀式がありました。たとえば、修験道にもそういった儀式としての機能が含まれています。修験道とは、山での修行を通じて悟りを開くことを目的とする山岳信仰ですね。
修験道では、山を登らせることによって、子どもを大人に「生まれ変わらせる」儀式があるんです。15歳になった子どもを、一人で山に登らせるのですが、そのルートの途中には「のぞき」と呼ばれるかなり危険なポイントがあるんです。まさに断崖絶壁で、一歩足を踏み外せば死が待っているような場所を、子どもは念仏を唱えながら越えていく。
なぜ、わざわざそんな危険な場所を通過させるかと言うと、擬死体験をさせるためなんですよね。擬似的に「子どもだった自分」を死なせ、社会的に責任を持つ大人に生まれ変わるために、子どもたちは「のぞき」を越えるわけです。この儀式をきっかけに大人になり、住んでいる村でさまざまな仕事を任せられることになる。
「死」はまさに究極の「未知の世界」ですよね。その死を擬似的に感じることによって、「大人」としての新たな自分を発見すると。


山内
そういうことです。海外に行ってみることは、自分という器を知るために有効な一つの手段だとは思いますが、未知の世界は身近にも広がっている。「哲学」などの学問も、そんな未知の世界の一つだと思います。「私ならざるもの」に出会うことによって、「私」と出会う。私たちのご先祖様たちも、そんな道筋を通っていたのではないでしょうか。
「他者との違い」ではなく、「自分の好み」を追求する
先ほど「かつてよりも、『自分探し』が難しくなった」というお話がありました。自らの個性とは何なのか、あるいは個性をどう発揮すればよいかわからず悩んでいる方も少なくないと思います。私たちが「自分らしさ」を活かし、生きていくためにはどうすればよいのでしょうか?

山内
先ほど、私たちは「自分探し」を通して、好みのテイストを見つけていくというお話をしました。そこにヒントがあるのではないかと思っています。
「誰ともかぶらない何か」を「自分らしさ」だととらえると、とても苦しくなると思うんですよね。誰ともかぶらない才能やセンスを持っている人って少ないですし、それらしきものを無理に発揮しようとするあまり周囲から浮いてしまい、「出る杭」として叩かれてしまうこともあるでしょう。
でも、本当の「自分らしさ」って、「誰ともかぶらない何か」ではないと思うんです。それは、まさに「好み」に現れるのではないでしょうか。たとえば、同じラーメンを食べていても、胡椒を入れる人もいれば、もっと濃い味が好きだなと言う人もいる。そういった「好みの違い」こそが、「自分らしさ」なのではないかと。
同じものを見ていたとしても、それをどう感じるかは人それぞれですよね。


山内
それがハビトゥスの働きですし、そこに「自分らしさ」が表れるわけですね。先ほど言った「私とはハビトゥスである」という言葉にもつながります。
どこにもないメニューを開発することを目指すのでなく、どこにでもあるラーメンを自分好みの味に調整できるようになることが大事なのではないでしょうか。そういう意味では、突出した何かができなくてもいいんですよ。周囲と同じようなことをやっていたとしても、そこに“自分らしい味づけ”ができればいい。
そうすれば、「自分らしさ」と「他の誰からしさ」を明確に区別することはできないかもしれませんが、その間に横たわる微妙なグラデーションの中に「自分」を位置づけることができるようになると思うんです。「あの人の好みはもっと薄味で、あの人はもっと濃い味が好き。僕はその間くらいだな」といったようなイメージで。
つまり、「自分らしさ」を知るということは、「自分の好み」を知り、それを追求していくこと。それが他者とぶつかり合わない、「自分らしい」あり方につながるのではないでしょうか。
[取材・文]鷲尾 諒太郎 [撮影]須古 恵 [編集]小池 真幸