
【後編】吉岡 洋
「面白さ」は文明の原動力。AIにはない予測不可能性
美学研究者に聞く
2025.09.18
必ず肯定してくれるAIとの対話に対し、誤解やすれ違いなど、何が起こるかわからない人間とのコミュニケーション。
必ず寄り添ってくれる対話型AIに依存する人も増えていますが、「本当の思考はどこに行くかわからないもの」と、美学者の吉岡洋さんは言います。どこへ着地するかわからない不安定さは、面白さの源ともいえるのではないでしょうか。
前編に続き、著書『AIを美学する』でAIが人間にどのように現れているのかを扱う、吉岡さんに伺いました。美学の視点から考えると、AI時代における人間の価値はどこにあるのでしょう。そして、「面白いこと」の意味は?
( POINT! )
- 本当の思考は「どこに行くかわからない」
- 採点できる思考力はAIに代替可能
- 予測不可能な面白さ
- AIは人間の「心の断片」
- 美学とは利益に還元できない価値
- 面白さこそが文明の原動力
- 美的経験への「取り憑かれ」が発見に

吉岡 洋
1956年京都生まれ。京都大学文学部哲学科(美学専攻)、同大学大学院修了。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)教授、京都大学大学院文学研究科教授、同大学こころの未来研究センター特定教授を経て、現在京都芸術大学文明哲学研究所教授。専門は美学・芸術学、情報文化論。著書に『〈思想〉の現在形──複雑系・電脳空間・アフォーダンス』(講談社選書メチエ)、『〈こころ〉とアーティフィシャル・マインド』(共著、創元社)、『情報と生命──脳・コンピュータ・宇宙』(共著、新曜社)、『AIを美学する:なぜ人工知能は「不気味」なのか』(平凡社新書)などがある。YouTube「ひるねのたぬき」
人間の思考は、どこに行くかわからない
これまでの基準で「いい」とされているものはAIのほうがうまくできると、前編で伺いました。そうだとしたら、人間は能力の有無を問われることなく生きられるのではないでしょうか。

吉岡
人間の知的能力のなかの、AIで代替できるような部分には価値がなくなっていくということですよね。
はい。受験みたいなものも変わりますよね。

吉岡
時間内に情報処理して答えを出すようなことは、AI的な能力に近いですね。たとえば「東京大学に受かった人は賢い」というようなものが、あまり通用しなくなってきている。それは今ほどAIが広まる以前からはじまっていることですが。
そうですね。体験を重視する流れが起きていますが、それはそれで豊かな人に有利になっているといわれています。

吉岡
そこは逆説的な部分がありますね。記憶を詰め込むような内容ではなく、主体的な思考力やコミュニケーション能力を重視するようになってはいるけど、試験の枠組み内で試せる思考力のようなものは、たいしたものじゃないんですよ。採点できるものなので。
本当の思考はどこに行くかわからないもの。最終的に採点して点数に還元できるようなものは、どうでもいいものなんですよ。そうした思考はむしろAIに置き換え可能なもので、人間独特の主体的な思考ではありません。だからかえって、キツくなっているような感じがしますね。
キツくなっている?

吉岡
昔の受験生は、どれだけ覚えられるかという量を争っていました。量では機械に勝てるはずないんだけど、ねじり鉢巻きで徹夜して勉強してあいつが受かった、俺は滑ったみたいなことをやっていたことのほうがむしろ人間らしい気がします。
『キテレツ大百科』の勉三さんのようなかわいらしさがありますね。

吉岡
人間的な(笑)。ゆとりを持って自由な思考力や作文する能力を重視するという今のほうが、機械みたいになってるという逆説があります。バランスが取れすぎてると、面白くないんですよね。

AIに驚くのは、人間の心に反応すること
人間の思考はどこへ行くかわからないものとのことですが、そうした予測不可能性と不完全さには「どうなるかわからない」面白さがありますね。現時点でAIは基本的に肯定してくれるものなので、偏りやジレンマを抱えて、何を返してくるかわからない人間が肯定してくれたときのほうが喜びがあります。

吉岡
それはわかります。AIに関心があって新しいものは使ってみるけど、すぐ飽きちゃう。もういいや、わかったって。心の底では、人間と対等なものと見てないんでしょうね。面白いけど、違う種類のものだと思っている。
ChatGPTの「GPT-5」が登場して、親しみが失われたと話題になりました。対話型AIに求められているものは、賢さだけではないということでしょうか。

吉岡
ChatGPT以降のAIとのやり取りが一定のレベルを超えたので、人間が驚いて関心を持ったり脅威を感じたりしています。それ以前のやり取りでは「やっぱり機械だな」という安心感みたいな特徴があった。それが人間と機械の間の心理的な境界線をつくっていたと思うんです。
それが超えられたということなんだけど、実は昔だって驚いていたんです。
初期の人工知能とか。

吉岡
そうです。1960年代に登場したELIZA(イライザ)はパターンで対話できるプログラムで、今のAIのような言語能力を持つものではありませんでした。それでも「境界を超えた」と感じた人は多かったんですよね。
人工知能には冬の時代と呼ばれる停滞期があって、2000年代以降に急速に発展しました。インターネットの拡大でデータの蓄積が大量にできたこと、コンピューターの処理能力が上がったこと。そういう条件が揃ったことで起こったんですね。
それでも、コンピューターは基本的に人間の心がかつて生み出した文字や映像・データを組み合わせて返しているわけなので、ChatGPTの答えに「もう人間と変わらないんじゃないか」「まるで人間みたいだ」「心を持ってるみたいだ」と僕らが感じるのは、人間が吐き出した心の断片に反応してるってことなんですよ。
人間でできているということですよね。

吉岡
フランケンシュタインの怪物のように、つぎはぎでできていますね。
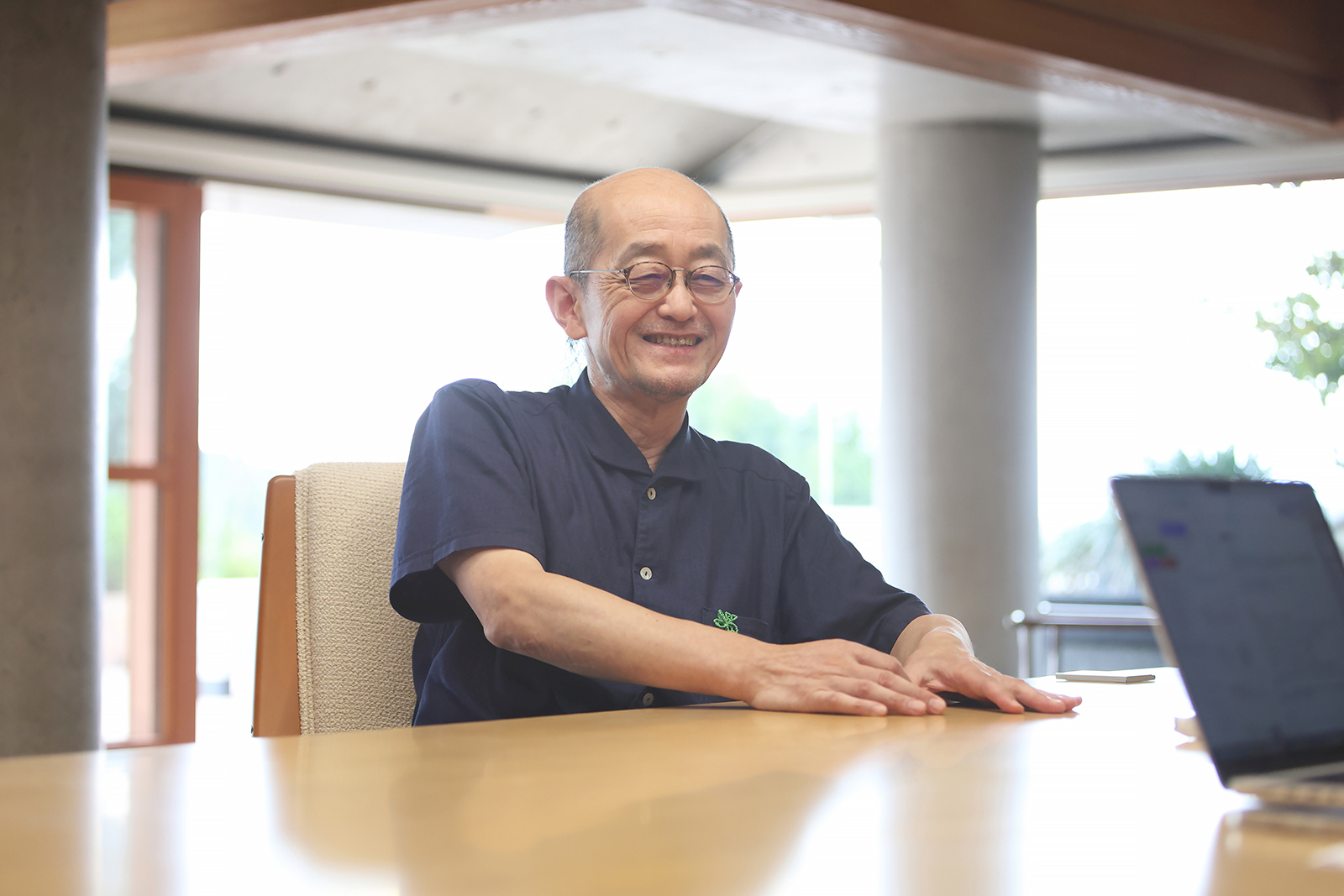
面白さこそ、文明の原動力
ChatGPTに親近感を求める声が多いのも、人間とのコミュニケーションに共感を求める人が多いからということですよね。吉岡さんの『AIを美学する』は、AI対人間という構図ではなく「美学する」側面から書かれています。そもそも、美学って何なのでしょう。

吉岡
「◯◯の美学」って言うじゃないですか。
「ラーメン屋の美学」とか?

吉岡
そうです。ラーメンだったら安くて美味しくあってほしいとか、満たすべき条件があります。それは技術的なことで、他にもいろんな特徴がありますよね。
普通は利益率が落ちるからやらない、面倒なダシの取り方をするとか。

吉岡
そんなふうに利益や数値的なものに還元できない、しかし価値を置きたいと人間が思うようなところにおそらく「美学」という言葉が当てはまりますね。「哲学」はいろんなものを扱えるけど、そのなかの人間の感性と感情とか、経験のなかの理屈に回収できない部分。そこを専門とする領域のことです。AIを美学するということは、AIが人間にどのように現れているのか、人間はそれをどう感じてるかを扱うということですね。
『AIを美学する』の感想で、「面白いけど楽観的すぎる」と言われたんですよ。これから起こりうる恐ろしいことについて書いていないと。
不安をあおったほうが注目を集められますね。

吉岡
予測不能なことが起こる可能性はもちろんあります。でも、美学にはオプティミスティックな傾向があるんです。「世界が終わる」みたいなことは言わない学問なんですよね。AIと人間との対立構造はないと考えているし、面白さを見出していくことの方が大事だと思っています。
「面白いこと」はなぜ重要なんでしょう。

吉岡
面白いことは、人間の心が自発的に動くことなんです。興が乗るという状態で、それは人類の文明の原動力なんですよ。
たとえば科学は、推論や実験を組み合わせて合理的に進んでいくと思われているけど、そうじゃない。映画『オッペンハイマー』の天才科学者のように、取り憑かれるんですよ。彼は核分裂の連鎖反応を起こすためにはどうしたらいいかを、まだ誰も成功してないときに考え続けます。それは美的な経験なんですね。それがないと、新しいテクノロジーや科学上のブレイクスルーが起こらないんです。
こういうものができたら役に立つとかお金が儲かるかといった合理的な目標があって、それに向かって努力して達成したんじゃないんです。取り憑かれて心が動かされてしまって、結果として何かが起こったという感じだと思うんですよね。
人間の科学的探求から日々の仕事まで、美学的な側面はいたるところにあります。しんどいと言いつつ仕事をするのも、どこか面白いからやっているんです。ネガティブなものであっても、人間の活動の根底には美的なものがあります。AIの発展も、美的な経験があるからすすむのだと思います。
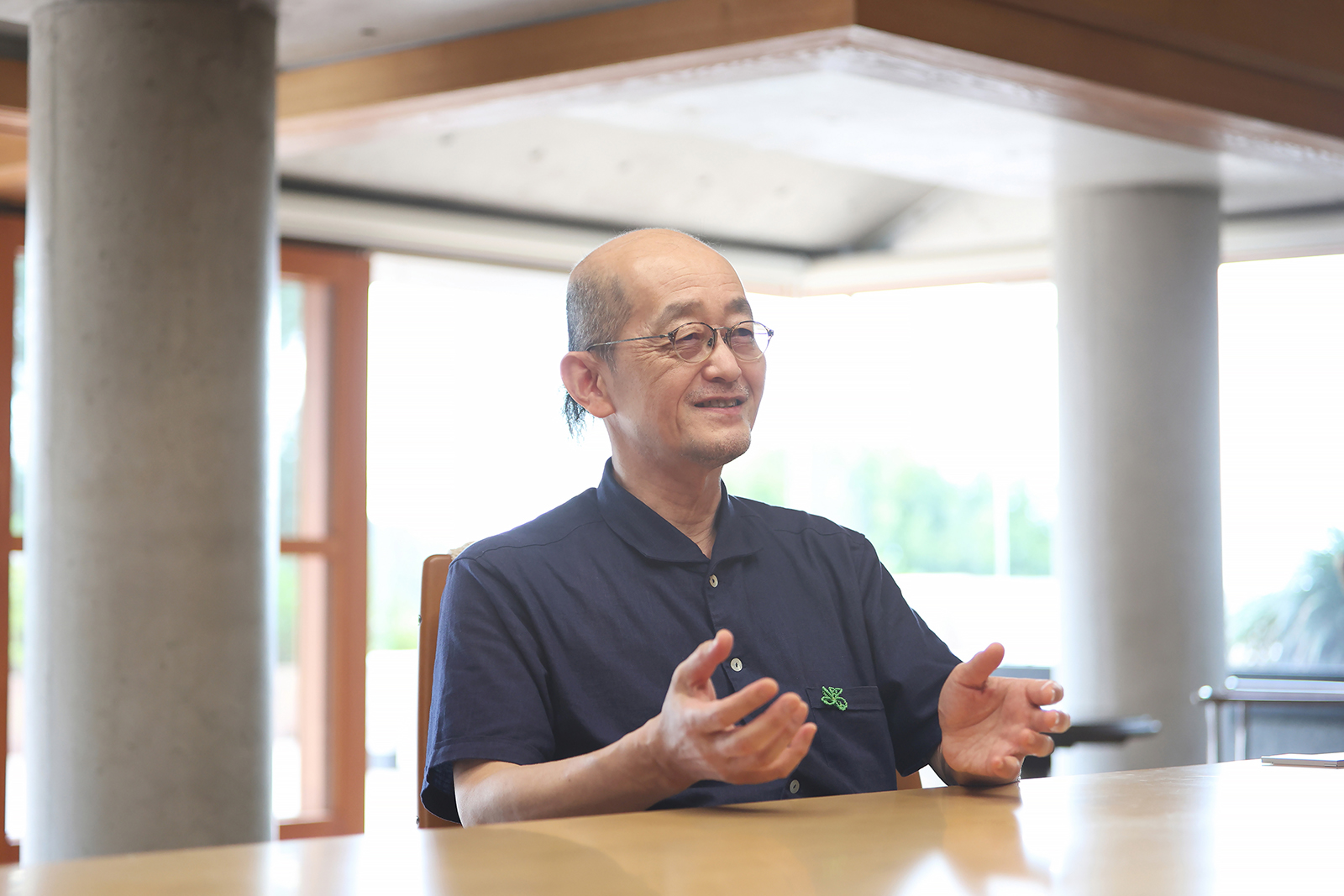
[取材・文]樋口 かおる [撮影]木村 充宏






