
【前編】毛内 拡
AIより省エネな脳。「能力」も「性格」も変えられる?
脳科学者に聞く〈脳を使いこなす〉方法
2025.08.21
「がんばれないのは気合いが足りないから」「自分の性格はこうだから、変わらない」
本当にそうでしょうか。
AIの実用化によって「能力」の定義が変わりつつあります。私たちの脳はどんな仕組みで能力を生み出しているのでしょう。脳科学者・毛内拡さんは「能力も性格も生まれつき固定されたものではなく、日々変わり続けている」と言います。
もし変化できるものならば、よりよく変えていきたいものです。でも現実には、思い込みにとらわれたり、やる気そのものが出なかったりすることもあります。『心は存在しない』『世界一やさしい脳科学入門 やる気が出ない理由は脳に聞いてください』など、多数の著書を通じて脳と人間の関係を探求する毛内さんに伺いました。
そもそも脳はどんな存在で、どんな働きをしているのでしょうか。
( POINT! )
- ヒトを人間たらしめるものへの問い
- 脳も細胞からできている
- ハードウェアとして脳を解き明かしたい
- 心は脳の副産物
- 脳にはシナプス可塑性がある
- 脳は省エネ
- 脳は予測をつくり出す装置

毛内 拡
脳科学者。1984年、北海道函館市生まれ。東京薬科大学生命科学部卒業。東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員を経て、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教。生体組織機能学研究室を主宰。「いんすぴ!ゼミ」代表。著書に『脳を司る「脳」―最新研究で見えてきた、驚くべき脳の働き』(講談社ブルーバックス)、『すべては脳で実現している。』(総合法令出版)、『面白くて眠れなくなる脳科学』(PHP研究所)、『「頭がいい」とはどういうことか―脳科学から考える』(ちくま新書)、『心は存在しない 不合理な「脳」の正体を科学でひもとく』(SB新書)、『世界一やさしい脳科学入門 やる気が出ない理由は脳に聞いてください』(河出書房新社)など。
「ハードウェアとしての脳を解き明かしたい」
著書『頭がいいとはどういうことか』『心は存在しない』など、毛内さんは脳科学を出発点に、人間や社会のさまざまなテーマを考察しています。そもそも、脳科学に興味を持ったきっかけはなんですか?

毛内
高校時代、ボランティアクラブでの活動で特別支援学校の運動会に参加した経験が原点になっています。それまでは自分に近いタイプの人たちと過ごすことが多かったので、忘れがたい体験になったんですよね。
違いを感じてショックを受けたということですか?

毛内
いえ、むしろ全然違わないことに驚いたんです。重度知的障害の方が多いと聞いて、「一緒にできないこともあるのかな」と想像していました。でも、実際に手をつないで走ったり玉入れをしたりしてみたら、運動機能も変わらないし、同じように勝てばうれしくて、負けたら悔しい。基本的な部分は何も変わらないと気づいたんですよね。
でも、僕らは大学受験真っ盛り。数学や科学の問題を素早く効率的に解くという、いわゆる知的能力を競っていた時期です。ふと、「能力を競うことって本質的なのかな?」と疑問を持ちました。そこから「人間とは何だろう、ヒトを人間たらしめるものは何なのだろうか」と考えはじめ、夢中で答えを探すようになりました。
どんな方法で答えを探したんでしょうか。

毛内
AIはもちろん、インターネットでもそれほど情報が得られない時代だったので、図書館でたくさんの本を読みました。心理学、生物学、医学、宗教学、哲学などです。でも、どこにも答えらしきものを見つけられなくて。ただ一つわかったのは、おそらく「既存の学問に明確な答えはない」ということです。
当時は脳科学が流行りだした頃で、養老孟司さんや 澤口俊之さんの本も読みました。そしてぼんやりと「違いがあるとしたら、心ではなく脳に関係しているのではないか」と考えるようになりました。それで、脳についてちゃんと研究したいと思ったんです。
そこで、最短距離で脳の研究ができそうな進路を探しました。心理学ではなく生物学を選んだのは、立花隆さんと利根川進さんの『精神と物質』という本の影響です。脳も細胞からできていて、生物学は可能性の塊だと知りました。そこで脳や脳内物質について、ふんわりとした理解ではなく、ハードウェアとしてきちんと解き明かしていきたいと思いました。

脳の「可塑性」。能力も性格も変わり続ける
がんばれるか、能力があるかどうかなどは、ソフトウェア的な問題ととらえられることが多いですよね。

毛内
「気合いでどうにかなる」みたいなことを言われますよね。
気の持ちようではなく、脳の働きには仕組みがあるということですか。

毛内
はい。脳神経学者の中田力さんの『いち・たす・いち:脳の方程式』という本には脳も自然科学に属する以上、究極的には数式で表せるはずだと書かれていて、とても感銘を受けました。
脳というものが物理現象として存在する以上、必ずメカニズムがあり、説明できて数式で表せます。脳を物質として理解する必要があるし、心は脳の副産物というか、働きの一部に過ぎないだろうということです。そこに早く気付けたのはよかったなと思います。
脳には仕組みがあるとのことですが、生まれ持ったものだから仕方がないということではないですよね。毛内さんの著書『世界一やさしい脳科学入門』では、脳の変化し続ける性質が説明されています。

毛内
そうです。脳には「シナプス可塑性(*1)」があるので、変化することができます。
勉強や仕事で成果が出せないと、「遺伝だから仕方がない」「才能がない」と思うことがありますが。

毛内
「生まれつき持っている遺伝子の影響があるから、その人は本来こういう人である」とするのは、本質主義という考え方ですね。それは思い込みにとらわれている部分が多いです。筋力や反射神経など遺伝的な才能も存在しますが、遺伝だけですべてが決まるという考えは単純すぎます。
スポーツ選手の子どもがスポーツ選手になると「遺伝のおかげ」と思いたくなりますが、スポーツ選手である親が練習環境や専門的なサポートを整えている影響もあります。また、スポーツ選手である親のふるまいを身近で見ることによって得られる食事の仕方やトレーニング習慣など、「知恵ブクロ記憶(*2)」の影響も大きいです。
能力も性格も、遺伝子や親ガチャといった見えないものや誰かのせいで固定されるものではないんです。
性格もですか?科学的な根拠を持たない性格診断も人気ですし、自分には「本来の性格」があるような気もしています。

毛内
性格ももちろん変わります。人間の脳は生まれたときは白紙のような状態。そこに言語や文化など日常生活からの刺激が加えられ、思考の癖などがつくられていきます。脳は年齢を重ねても可塑性を保つので、その変化もずっと続いていくんです。
脳の地図は日々書き換わります。遺伝と環境は対立するものではなく、遺伝子は設計図。遺伝子の発現を後天的に調節する仕組みを「エピジェネティクス(後成的遺伝子発現制御)といいます。つまり、どれだけ優れた遺伝子を持っていても、経験や環境が伴わなければ実力が十分に発揮されることはないんです。

脳は「省エネ」。予測をつくり出す装置
脳の仕組みを知ることで、能力や性格を変化させられるということですね。ところで、脳をうまく活用したいと思っても、どうしようもないことをくよくよ考えてしまったり、ポジティブな選択を取れなかったりすることがあります。脳が私たちを「よりよく生かそう」としているのであれば、矛盾を感じます。

毛内
脳が全然合理的じゃない動きをするということですよね。
そうです。だから脳の目的は何なのだろう、と思ったんです。

毛内
一言でいうと、脳は予測をつくり出す装置なんです。
そもそも、脳はめちゃくちゃエネルギーを使います。なぜエネルギーを使うのかというと、僕らは昔は海に住んでましたよね。変温動物だったけど、その後、恒温動物になりました。歩きながら呼吸できるようになったけど、エネルギーもたくさん使うようになったから食べ続けなきゃいけなくて。ヒトの脳のハードウエアとしての基本的な設計は10万年ほど前からさほど変化していないと言われています。そして、脳のエネルギーとなるものはブドウ糖です。
今は糖質制限が必要な人も多いくらいですが、昔は今ほど簡単に糖が手に入りませんでした。だから省エネになるよう設計され続けたんですね。進化生物学的に考えると特に目的はなくて、よいほうへ行くだけなんです。
よいほうへ行く?

毛内
よく誤解されているんですが、キリンの首が長いのは高いところの葉をたくさん食べたいと思ったからじゃなくて、たまたまそういう個体が残っているだけで。
なるほど。

毛内
脳の進化も「こうなりたい」という目的があるのではなく、たまたまそうなって、うまくいったから残っているということ。そして省エネ戦略として、思考もショートカットするわけです。
そもそも脳って、体重の2%しかないのに、基礎代謝の20%は脳が使っています。そしてどうやって省エネするかというと、推論を使ってショートカットします。たとえばスーパーでお醤油を探すとき、棚の端から端まで商品を全部見ることはありませんよね。過去の記憶と経験から「きっと調味料コーナーにあるだろう」「調味料コーナーは真ん中あたりかな」と予測を立てて、そこへ向かいます。これは「ヒューリスティック」という推論を使っています。
一方、AIやアルゴリズムが同じことをする場合、その店の在庫をAから全部スキャンし続けて、Sでようやく「醤油」を見つけるということになります。全然効率的じゃないですよね。
いわゆる「脳筋」的な、力技ですね。

毛内
そうです。脳は省エネしたいから、力技ではなく過去の経験や記憶から「こうなってるだろう」という脳内モデルをつくります。そして目や耳を使った実測と比較して違いがあれば、脳内モデルを書き換えてアップデートするようなことをやっているんですよね。
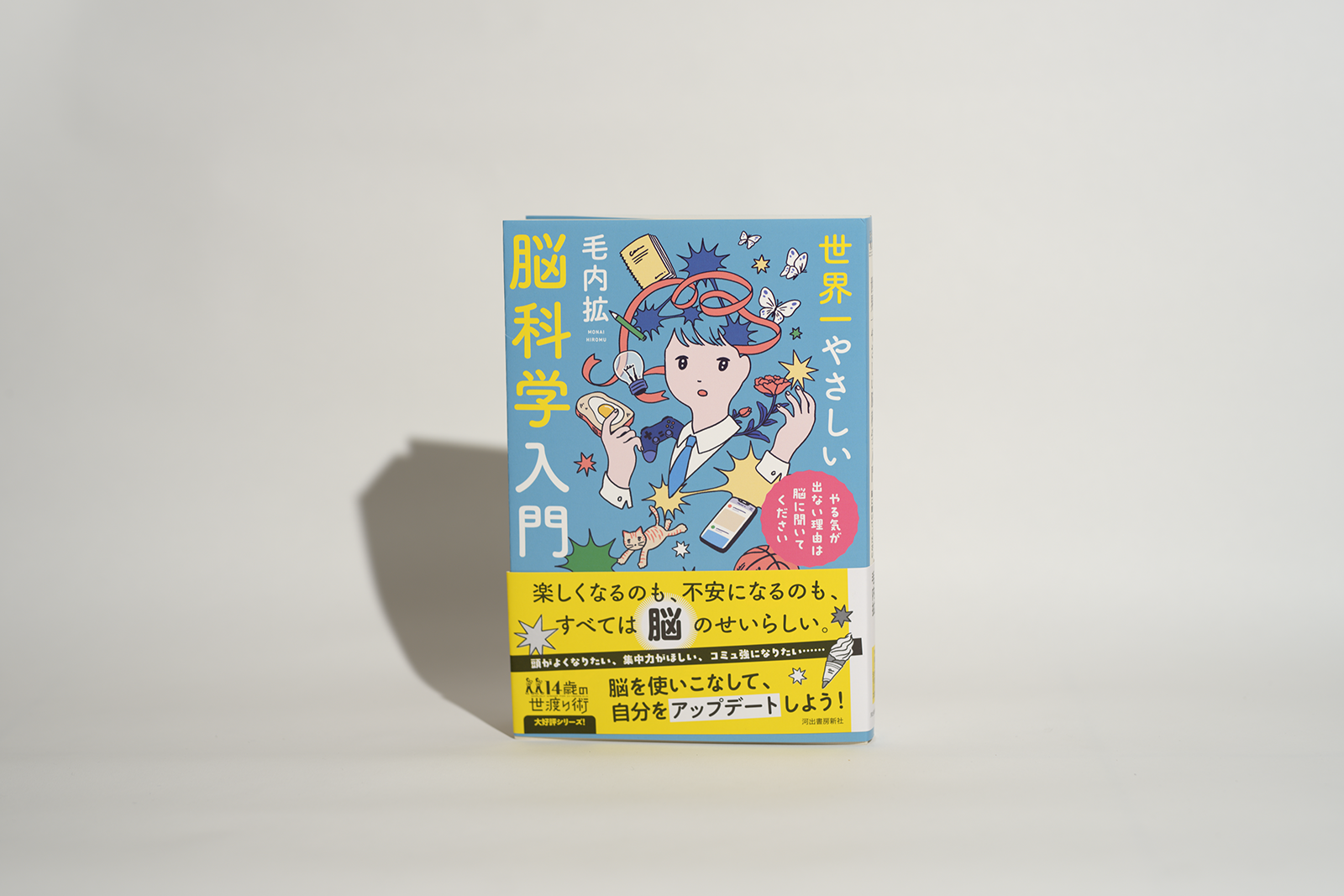
脳には可塑性があり、能力や性格も変えられること。さらに、脳が「脳内モデル」をつくって予測していることも伺った前編はここまで。脳の仕組みを知れば、私たちはもっと柔軟に変わっていけるのかもしれません。後編では、「なかなか思い通りに動いてくれない脳」とどう付き合えばいいのか、そのヒントを伺います。お楽しみに。
- ※1:
- ニューロン(神経細胞)同士のつながりが強まったり弱まったりして変化できる性質
- ※2:
- 経験や記憶から培われた記憶の集まり。毛内さんが提唱
[取材・文]樋口 かおる [撮影]野間元 拓樹






