
【後編】山口 真一
騙されやすい私たち。アテンション・エコノミーとどう付き合う?
仕組みを知り、自覚的に選択を
2025.03.13
無料で見られる動画や、次々に生み出されるコンテンツ。背景には、私たちの関心をお金に変える「アテンション・エコノミー」があります。自分の興味関心が収集され数値化されることを不安視する人もいますが、好みのコンテンツに出会えたり、広告を閲覧することで無料で利用できたりするメリットも。特に意識することがなかったとしても、ネット環境を利用するうえで誰もが関わっている経済原理といえるでしょう。
でも、個人が収益をインセンティブに情報を発信したり拡散したりすることで、フェイクニュースが広まったり政治的な影響を与えたりする可能性もあります。問題はないのでしょうか。前編に続き、ネットメディア論の専門家で『ソーシャルメディア解体全書』の著者でもある山口真一さんに話を伺いました。
( POINT! )
- アテンション・エコノミーの背景にある広告
- 過激なものが拡散されやすい
- よい情報か悪い情報は判断しづらい
- 法規制もすすんでいる
- 切り抜き動画など新しい手法も増加
- 騙されやすいことを自覚する

山口 真一
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授。1986年生まれ。博士(経済学・慶應義塾大学)。専門は計量経済学、社会情報学、情報経済論。NHKや日本経済新聞をはじめとして、メディアにも多数出演・掲載。KDDI Foundation Award貢献賞、Nextcom論文賞、組織学会高宮賞、情報通信学会論文賞(2回)、社会情報学会論文奨励賞、電気通信普及財団賞、Web人賞、紀伊國屋じんぶん大賞を受賞。著作に『正義を振りかざす「極端な人」の正体』(光文社)、『なぜ,それは儲かるのか』(草思社)、『炎上とクチコミの経済学』(朝日新聞出版)、『ネット炎上の研究』(勁草書房)、『ソーシャルメディア解体全書:フェイクニュース・ネット炎上・情報の偏り』(勁草書房)など。他に、早稲田大学ビジネススクール兼任講師、シエンプレ株式会社顧問、株式会社エコノミクスデザインシニアエコノミスト、日経新聞Think!エキスパート、日本リスクコミュニケーション協会理事、日本テレビ放送番組審議会委員などを務める。また、内閣府「AI戦略会議」を始めとし、総務省、厚生労働省、公正取引委員会などの様々な政府有識者会議委員を務める。
コンテンツが無料で楽しめる仕組み
アテンション・エコノミーが拡大してきた背景には様々な要素がありますが、特に大きな要素として広告の存在がありますよね。

山口
それは間違いないと思います。たとえば動画共有サービスでクリエイターがお金を儲ける場合、ファンを増やして作品を買ってもらうこともありますが、多くの場合は視聴数に応じた収益がメイン。広告を見てもらった分が収益になるということです(*1)。
視聴者側は無料でコンテンツを楽しめて、クリエイターの収益にもなる仕組み。

山口
そうですね。無料なのでいくらでも見られるわけですが、プラットフォームはYouTubeだけではなくマスメディアもネットメディアも多数あります。情報提供競争になりますので、コンテンツも溢れてしまう。そうなってくると視聴者側に足りないのはお金ではなく時間です。
「検索して自分の求めている情報を得る」ことは実際コストのかかる作業なので、プラットフォーム側がその人の見たいであろうものを優先的に表示しています。履歴などを分析してレコメンドする。便利ですが、フィルターバブルやエコーチェンバー現象が起きてしまう問題もあります。
1回見ると同じような動画がたくさん表示されて、「ものすごく流行っているんだな」と感じます。

山口
アルゴリズムも非常に最適化されているので、レコメンドされるとつい見てしまうことになりやすいですね。そのようななかで、コンテンツを提供する側は「どうしたらコンテンツを見てもらえるか」を考えます。その結果、起きる行動の1つに「過激なコンテンツを出す」ことがあります。
渋谷スクランブル交差点にベッドを置いたYouTuberもいましたが、それも「過激なことをして注目を集めてお金を得よう」という動き。よい情報も悪い情報も関係なく見られてクリックされればお金が入り、たくさん見られているのでさらに表示されるという仕組みでは、迷惑な行動やフェイクが拡散されやすくなってしまいます。

よい情報と悪い情報。線引きは可能?
広告主もよいコンテンツに広告を表示したいのではないかと思いますが、現状ではその区別が難しいということでしょうか。

山口
もちろん、見られた数だけではない評価方法は様々検討はされています。たとえばYahoo!ニュースでは「学びがある」「わかりやすい」「新しい視点」と3つのリアクションを選べるようになっています。よい取り組みですが、課題もあると思っています。
どんなことでしょう。

山口
まず、広告提供者にとっては「見られる」「購入される」など以外で評価をすることがそもそも難しいことがあります。どんなにいいものでも、知らないと購入したり利用したりすることができませんよね。ですから、認知度を向上させ潜在的消費者に届けることが広告の目的です。その観点からは、「学びがあるかどうか」は広告が成功したかどうかの判断基準になりにくい。
リアクションをする側についてですが、人は自分の考えに近いものじゃないと高く評価しない傾向があります。「学びがある」といった評価についても、結局過激で一部の人にウケるものがたくさん押されてしまう可能性があります。
好き嫌いで判断してしまうということですね。

山口
なんらかの規制を検討するにしても、表現の自由についての課題もあります。フェイクを過剰に規制してしまうと、それを利用して政府に批判的なジャーナリストや野党の議員の発言を統制することも可能になります。世界を見ればそのようなことは一般的に行われているので、やはり表現の自由は守らなくてはならないと思います。何がフェイクなのかも個人によって全然違うという状況がありますので、慎重にならざるをえません。
だからといってもちろん何もしなくていいということではありません。プラットフォーム事業者による取り組みは現在議論されているなかでも大事な要素。Yahoo!ニュースのコメント欄やTikTokには今、侮辱的なコメントに対してAIが「本当に投稿しますか?」とアラートを出す仕組みがあります。それを導入した結果、TikTokでは40%の人が投稿を修正するか削除したということで、非常に効果が高かったんです。
それは人々の行動変容を促すような機能であり、最終的な意思決定は人間が行っているので表現の自由を損なっていません。 そういった機能による環境改善にもっと取り組んでいく必要があると考えています。

誹謗中傷やフェイクニュースなどへの対策は
法規制などもあるのでしょうか?

山口
アテンション・エコノミーについて直接規制する法案はまだ出てないですね。総務省の検討会(*2)に参加していますが、そこでも議論された「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されます。インターネット上の誹謗中傷などへの対処の迅速化をすすめるもので、⼤規模プラットフォーム事業者に対して罰則規定もあります。フェイクニュースに関しては、表現の自由との調整があるものの、制度を作るということで現在議論をすすめているところです。
同じく参加している内閣府のAI戦略会議(*3)ではAIについても法整備をすすめることになりました。一歩一歩ですが、すすんではいます。
そうなんですね。「SNS政治」という言葉もありますが、演説を切り抜きショート動画にして収益化することで、多くの人に拡散してもらうような新しい手法も生まれています。

山口
2024年がSNS選挙の大きな転換点になりましたね。石丸現象といわれる現象では、石丸さん自身が街頭演説を短くしてインフルエンサーが配信してくれるように仕向けていました。それでSNSが盛り上がること自体はともかく、お金を稼ぐために特定の候補を応援したり配信したりするインフルエンサーが現れ、それで投票行動が変化する可能性には注意したほうがいいと思います。たとえば、選挙期間中は関連コンテンツの収益化を一部止めるといった対策が考えられます。
様々な動きがあるとは思いますが、Metaがファクトチェックを廃止するというようなニュースを聞くと、フェイクニュース対策が本当にすすんでいるのか不安になります。

山口
以前はプラットフォーム事業者には「自分たちには責任がない」という発言が多かったのですが、それは変わってきていますし、対策は強化されています。とはいえ、現在は1民間企業によるプラットフォームを言論のインフラのように使っている状態です。政治状況や、経営者変更によるその企業の方針転換によって、簡単に逆行することもありえるということが、改めて示された格好です。
そのような状況のなか、私たちがアテンション・エコノミーの悪い側面に飲み込まれずにいるにはどうしたらいいでしょうか。

山口
アテンション・エコノミーや個人のデータが分析されることが必ずしも悪いということではありません。若い人ほどデータ利活用にポジティブで、年齢が上がるにつれてネガティブになるという私の調査結果もあります(*4)。最適にリコメンドされた情報を楽しんでいる人も多く、問題は自覚的に選択していないこと。
アテンションがお金を儲ける仕組みに使われていること、過激なものほど拡散されやすい環境にいるということをまず知っておく必要があります。私の研究では、偽・誤情報を見聞きしたあとそれを見抜ける人は14.5%しかいませんでした(*5)。AIを使った偽の証拠などの見極めも非常に難しくなっています。常に「自分も騙されるかもしれない」という謙虚な気持ちで、情報空間に接することが大事な心がけになると思います。
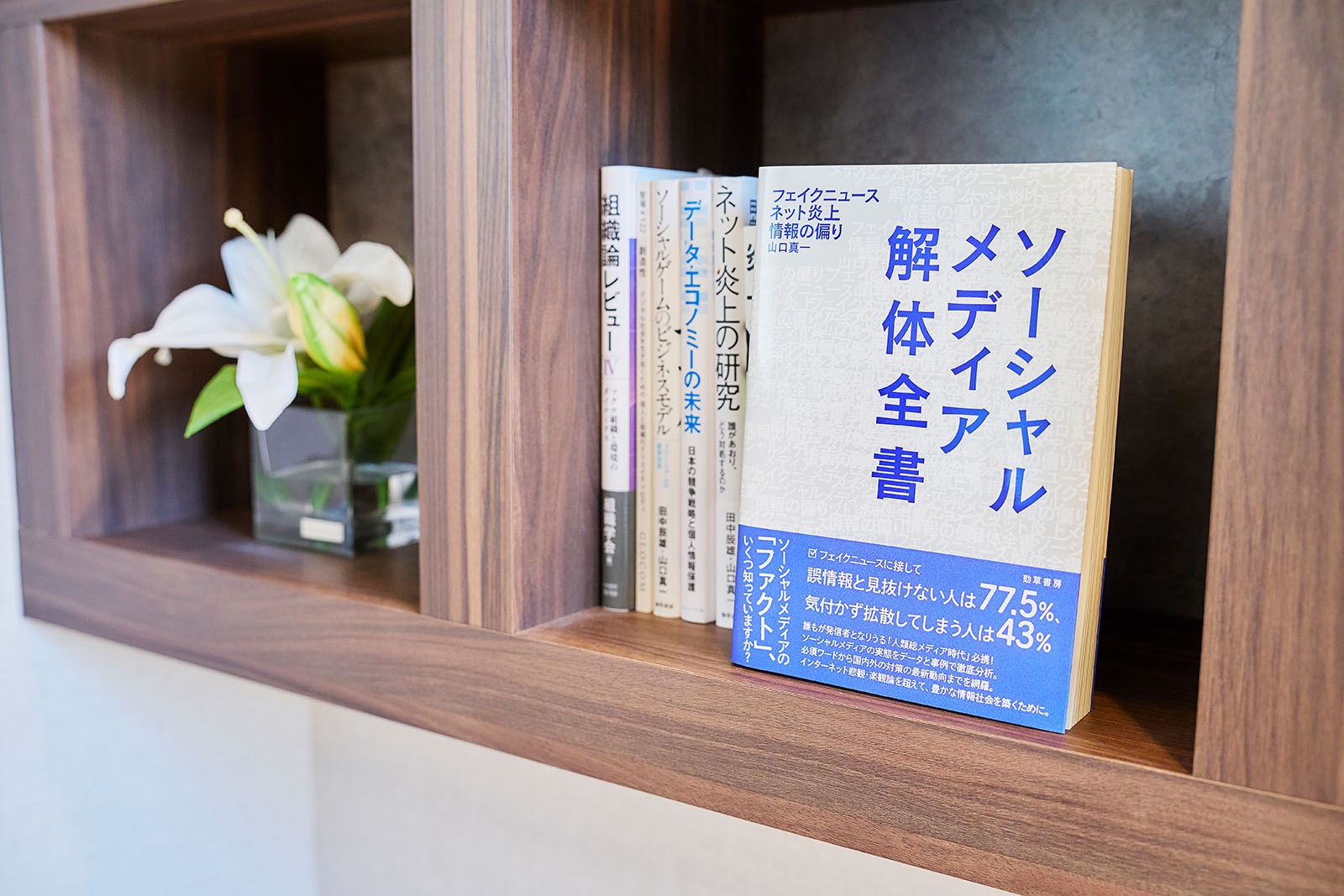
- ※1:
- YouTubeの場合、プレミアム会員になると広告を非表示にできる
- ※2:
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_shokadai/index.html
- ※3:
- 内閣府 AI戦略会議 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/ai_senryaku.html
- ※4:
- Yamaguchi, S., Oshima, H., Saso, H., & Aoki, S. (2020). How do people value data utilization?: An empirical analysis using contingent valuation method in Japan. Technology in Society, 62, 101285. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101285
- ※5:
- 山口真一ほか(2024)「Innovation Nippon 2024 偽・誤情報、ファクトチェック、教育啓発に関する調査研究」、 https://www.glocom.ac.jp/activities/project/9439
[取材・文]樋口 かおる [撮影]小原 聡太






